2009年4月、乾季のピークを迎えるマリに降り立ちました。
首都バマコから滞在先となるモプティへ向かう車中で、これまでと比べて、道路のでこぼこや年代ものの車が減っていることに気づきます。道沿いに建設された工場らしき建物や低所得者向けの新しい家の数々。変化を感じられる状況に、3回目となる視察への思いが高まりました。


モプティから55km離れたチャアラ村。コンクリートで舗装された道路からは車で5分ほど、町とのアクセスが比較的よい場所です。しかし、この村には安心して飲める水はありません。ダイナマイトを使って穴を掘り、壁面を石などで固めた井戸の水は、砂やほこり、ごみなどが混ざり、白く濁っています。囲いのない井戸の足場は、水で滑りやすく、この3年ほどの間に、家畜のほか、大人を含め10人が井戸に落ちたといいます。そのうち、7人が10歳前後の女の子でした。
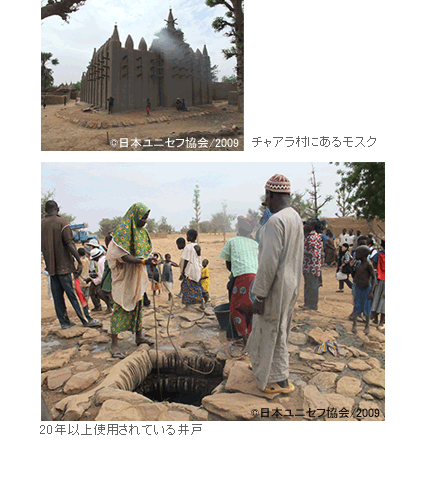

親戚を含め20人以上の家族と暮らしているアイサタ。アイサタをはじめ、親戚の女性はみな、バケツを持って、日に何度も水を汲みに来るといいます。ある日、アイサタは足を滑らせ井戸に落ちました。10時間以上かけて、村の人が救い出したとき、アイサタの体は冷え切り、その後、かぜをひいたといいます。
「また落ちるかと思うとこわい」、しかし、毎日、水汲みをしなくてはいけません。
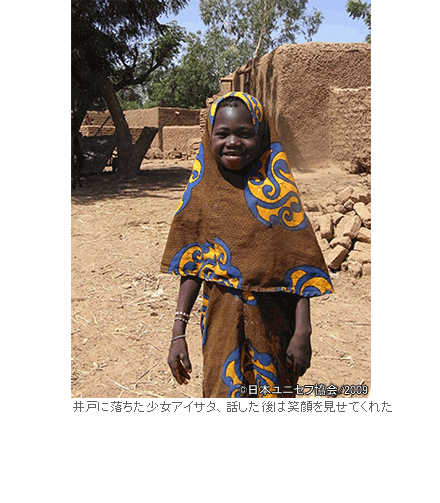
かつて、寄生虫病であるメジナ虫病が発生したチャアラ村には、予防のために、ろ過用のフィルターが配布されています。しかし、フィルターで取り除ける不純物には限りがあります。白く濁った水は、メジナ虫病の予防には有効なものの、決して安心して飲める水ではありませんが、「フィルターを使うようになってから、体調が悪い人は誰もいない。」と村長がいらだちながら、繰り返します。
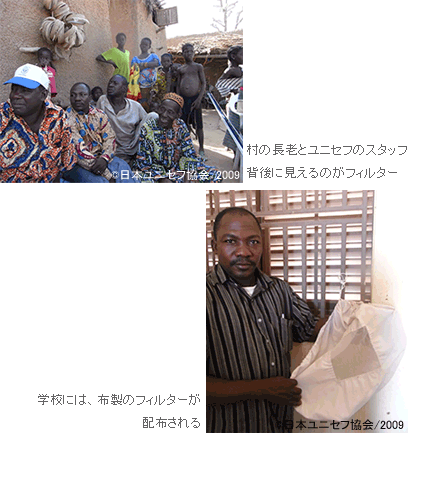
時間をかけて話をするなかで、わかったことは、思いもよらないことでした。「水に関する問題はありませんか」という質問を、村長は「正しくフィルターを使えているのか」と受け取っていたのでした。その質問を何度も聞かれることに、「メジナ虫病は発生していないのに、正しく使っていないと思われているに違いない。」と思い、「指導されたとおりにやっている。だから、メジナ虫病の人は誰もいないし、水に関係する問題はない。」と主張しているのでした。
たしかに、村には予備のフィルターも用意されており、2004年以降、メジナ虫病は発生していません。しかし、一方で、慢性的な栄養不良にある子どもたちが多く見受けられ、子どもたちの健康状況が望ましくないことは明らかです。
メジナ虫病根絶への村の人たちの努力を認める一方で、「それとは別に」と前置きをして、「体調が悪いことはありませんか」と尋ねてみました。すると、体がだるい、おなかが痛い、痛さのあまりまっすぐ立てないこともある、便に血が混ざっていることもある、などの話がどんどんと出てきます。
しかし、村の人たちは「原因は何かわからない」と言います。ユニセフのスタッフが「それは、みんなが飲んでいる水が、大きく関係がある。」と説明しても、「フィルターを使って飲んでいるから、だいじょうぶなはずだ。」との答え。状況、つまり体に現れている症状と、その原因である水との関係が、村の人たちには結びついていないのです。
チャアラ村の保健状況を知るべく、村から2キロ離れたブーゲル村にある保健センターを訪ねました。イギラ医師は「親の意識が問題だ。子どもの病気は、急激に悪くなる。症状が重くなってから、センターに来るため、手遅れとなるケースが多い。」と言います。
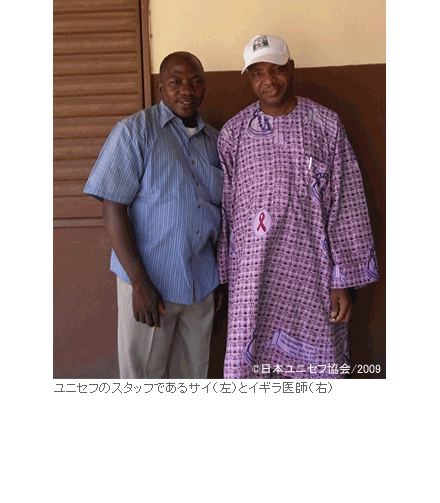
親が、子どもの体調の変化に気づいても、たいしたことはないと思い、そのままにしてしまうか、古くから伝わる民間療法を行う村人のところに連れて行ってしまうといいます。そして、容態が悪化してから、センターに連れてきます。症状が重いと、設備の整った町の病院に転送すべきだが「そんなにたくさんのお金は払えない。他の人に見せる。」と言って、子どもを連れ帰り、手遅れとなると言います。
イギラ医師は、「村の人には、お金の問題がある。それよりも、村人との間に、信頼関係が築けるかどうかが問題です。信頼してもらえなければ、誰も保健センターを訪ねてこない。村人の考え方やこれまでの習慣を上から見て、否定したり、自分たちの知識や情報を押し付けたりしては、決してうまくいかない。地道に、時間をかけて、ひとつずつ実績を作り、信頼してもらうのみだ。」と強く語ってくれました。
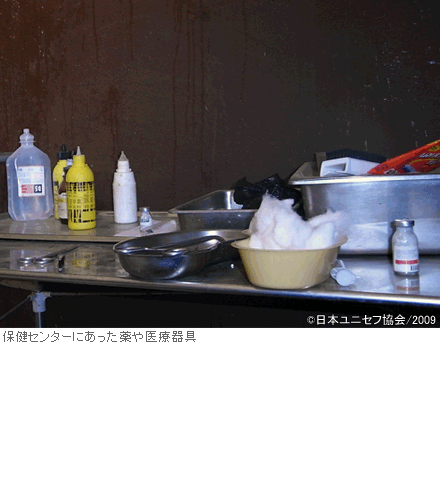
たしかに、他のセンターと比べて、2007年にできたこのセン
ターには、診察を待っている人も、スタッフの数も少ないのです。「1週間に訪れる人は、10人から15人。利用する人が多いとはいえない。」それでも、雨季になれば、マラリアや下痢にかかった子どもたちが増えます。薬などの在庫が足りず、適切な処置ができないこともありますが、「資金的な問題から、予備を含めた薬の在庫が十分に行えない」というのも現実です。「限られたなかで、できうる限りの予防と治療をしていくためには、信頼関係が欠かせない」保健センターで強く感じたことでした。
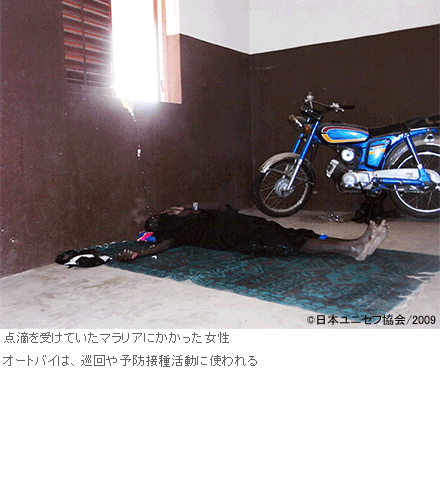
2009年4月、メジナ虫病根絶へ向けてのこれまでの取り組みと村の状況を踏まえて、ユニセフの支援活動の一環で、井戸がつくられることになりました。
これまでの井戸から比較的近いところに掘られた穴。
しかし、手押しポンプを取り付けるには、十分な水量が確保できず、場所を変えて掘削のやり直し。工事は、気温が下がる夜中も続けられました。
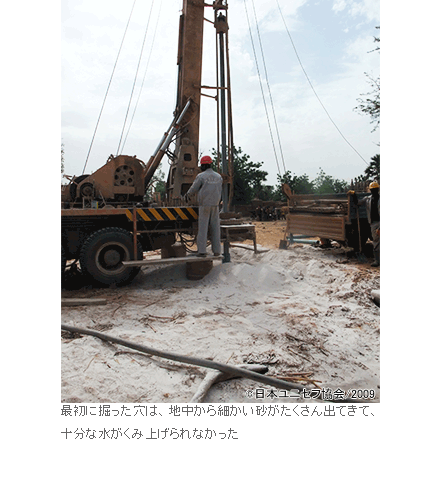
そしてその瞬間がやってきました。
掘削機の大きなモーター音のあと、地面からシュワシュワと水が出てきました。目を大きく見張って、徐々に笑顔を見せてくれる村の人たち。子どもたちの中には、歓声を上げ、手をたたく姿も。乾いた地面がぬかるみ、水たまりができました。

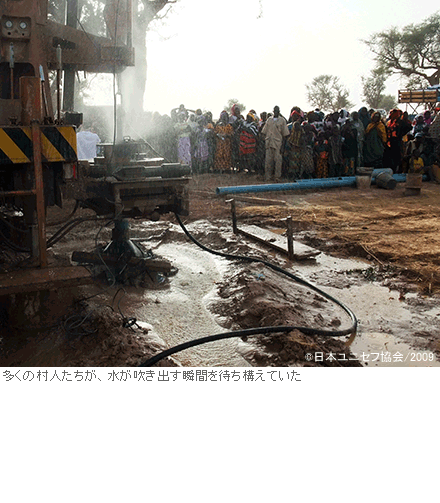
水が使えるようになれば、衛生的な生活が送れるようになり、健康状況が改善されます。これまで使っていた泥まじりの水は、家畜や農業に使えるようになります。水は、体だけでなく、生活をうるおしていく、そういう変化をこの2年間見てきました。
チャアラ村にも、同じ変化が訪れるはず、そう信じて、村を後にしました。
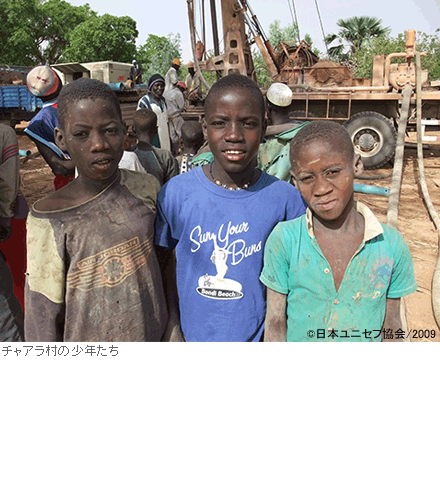
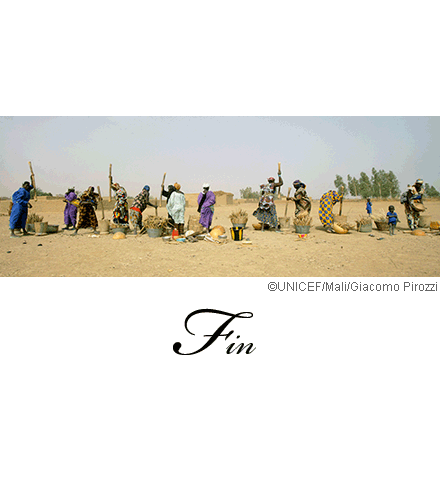
2009年4月、乾季のピークを迎えるマリに降り立ちました。
首都バマコから滞在先となるモプティへ向かう車中で、これ
までと比べて、道路のでこぼこや年代ものの車が減っているこ
とに気づきます。道沿いに建設された工場らしき建物や低所得
者向けの新しい家の数々。変化を感じられる状況に、3回目と
なる視察への思いが高まりました。

写真1,2

写真1,2
モプティから55km離れたチャアラ村。コンクリートで舗装され
た道路からは車で5分ほど、町とのアクセスが比較的よい場所
です。しかし、この村には安心して飲める水はありません。ダ
イナマイトを使って穴を掘り、壁面を石などで固めた井戸の水
は、砂やほこり、ごみなどが混ざり、白く濁っています。囲い
のない井戸の足場は、水で滑りやすく、この3年ほどの間に、
家畜のほか、大人を含め10人が井戸に落ちたといいます。その
うち、7人が10歳前後の女の子でした。
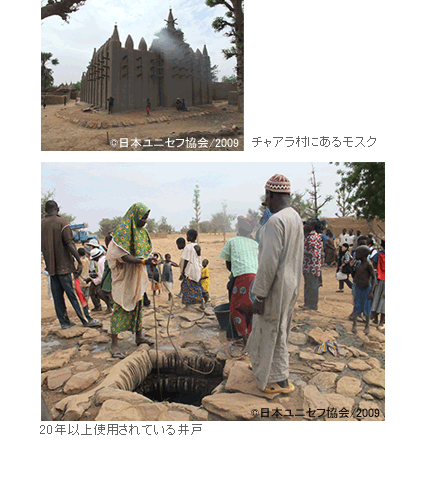
写真3.4.5

写真3.4.5
親戚を含め20人以上の家族と暮らしているアイサタ。アイサタ
をはじめ、親戚の女性はみな、バケツを持って、日に何度も水
を汲みに来るといいます。ある日、アイサタは足を滑らせ井戸
に落ちました。10時間以上かけて、村の人が救い出したとき、
アイサタの体は冷え切り、その後、かぜをひいたといいます。
「また落ちるかと思うとこわい」、しかし、毎日、水汲みを
しなくてはいけません。
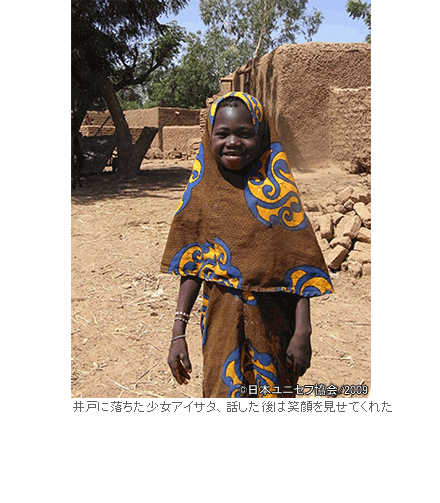
写真6
かつて、寄生虫病であるメジナ虫病が発生したチャアラ村には、
予防のために、ろ過用のフィルターが配布されています。しか
し、フィルターで取り除ける不純物には限りがあります。白く
濁った水は、メジナ虫病の予防には有効なものの、決して安心
して飲める水ではありませんが、「フィルターを使うようにな
ってから、体調が悪い人は誰もいない。」と村長がいらだちな
がら、繰り返します。
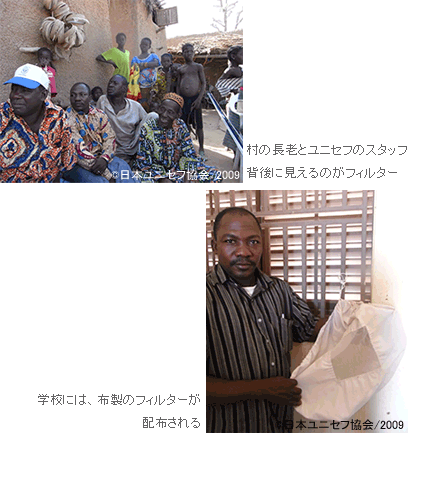
写真7.8
時間をかけて話をするなかで、わかったことは、思いもよら
ないことでした。「水に関する問題はありませんか」という質
問を、村長は「正しくフィルターを使えているのか」と受け取
っていたのでした。その質問を何度も聞かれることに、「メジ
ナ虫病は発生していないのに、正しく使っていないと思われて
いるに違いない。」と思い、「指導されたとおりにやっている。
だから、メジナ虫病の人は誰もいないし、水に関係する問題は
ない。」と主張しているのでした。
たしかに、村には予備のフィルターも用意されており、2004年
以降、メジナ虫病は発生していません。しかし、一方で、慢性
的な栄養不良にある子どもたちが多く見受けられ、子どもたち
の健康状況が望ましくないことは明らかです。
メジナ虫病根絶への村の人たちの努力を認める一方で、「それ
とは別に」と前置きをして、「体調が悪いことはありませんか」
と尋ねてみました。すると、体がだるい、おなかが痛い、痛さ
のあまりまっすぐ立てないこともある、便に血が混ざっている
こともある、などの話がどんどんと出てきます。
しかし、村の人たちは「原因は何かわからない」と言います。
ユニセフのスタッフが「それは、みんなが飲んでいる水が、大
きく関係がある。」と説明しても、「フィルターを使って飲ん
でいるから、だいじょうぶなはずだ。」との答え。状況、つま
り体に現れている症状と、その原因である水との関係が、村の
人たちには結びついていないのです。
チャアラ村の保健状況を知るべく、村から2キロ離れたブーゲ
ル村にある保健センターを訪ねました。イギラ医師は「親の意
識が問題だ。子どもの病気は、急激に悪くなる。症状が重くな
ってから、センターに来るため、手遅れとなるケースが多い。」
と言います。
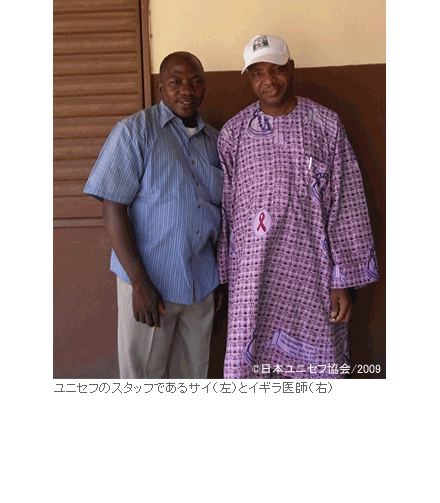
写真9
親が、子どもの体調の変化に気づいても、たいしたことはない
と思い、そのままにしてしまうか、古くから伝わる民間療法を
行う村人のところに連れて行ってしまうといいます。そして、
容態が悪化してから、センターに連れてきます。症状が重いと、
設備の整った町の病院に転送すべきだが「そんなにたくさんの
お金は払えない。他の人に見せる。」と言って、子どもを連れ
帰り、手遅れとなると言います。
イギラ医師は、「村の人には、お金の問題がある。それよりも、
村人との間に、信頼関係が築けるかどうかが問題です。信頼し
てもらえなければ、誰も保健センターを訪ねてこない。村人の
考え方やこれまでの習慣を上から見て、否定したり、自分たち
の知識や情報を押し付けたりしては、決してうまくいかない。
地道に、時間をかけて、ひとつずつ実績を作り、信頼してもら
うのみだ。」と強く語ってくれました。
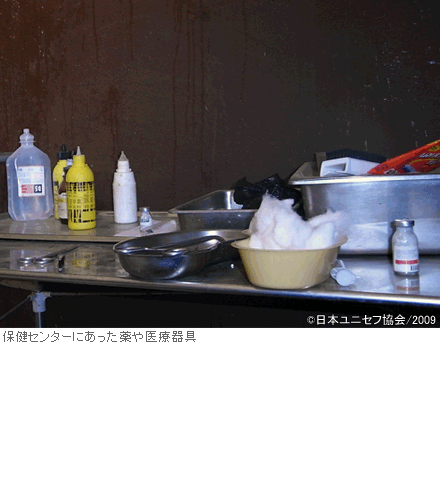
写真10
たしかに、他のセンターと比べて、2007年にできたこのセン
ターには、診察を待っている人も、スタッフの数も少ないので
す。「1週間に訪れる人は、10人から15人。利用する人が多い
とはいえない。」それでも、雨季になれば、マラリアや下痢に
かかった子どもたちが増えます。薬などの在庫が足りず、適切
な処置ができないこともありますが、「資金的な問題から、予
備を含めた薬の在庫が十分に行えない」というのも現実です。
「限られたなかで、できうる限りの予防と治療をしていくため
には、信頼関係が欠かせない」保健センターで強く感じたこと
でした。
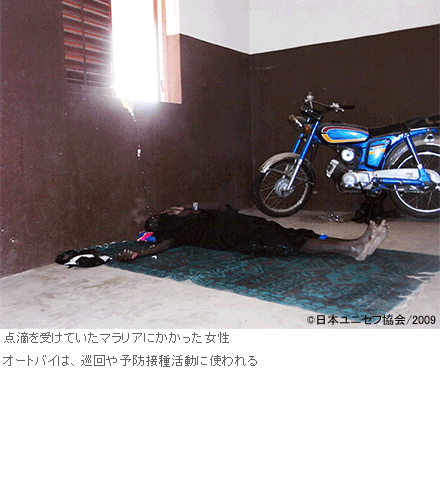
写真11
2009年4月、メジナ虫病根絶へ向けてのこれまでの取り組みと
村の状況を踏まえて、ユニセフの支援活動の一環で、井戸がつ
くられることになりました。
これまでの井戸から比較的近いところに掘られた穴。
しかし、手押しポンプを取り付けるには、十分な水量が確保で
きず、場所を変えて掘削のやり直し。工事は、気温が下がる夜
中も続けられました。
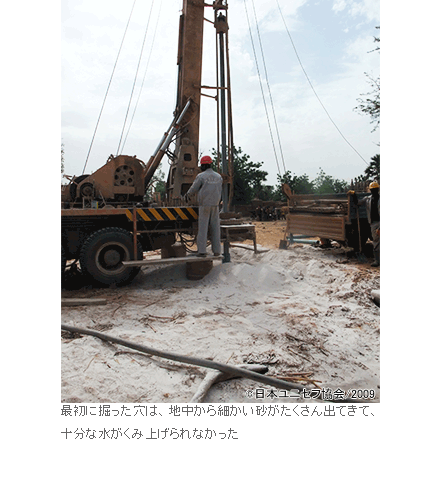
写真12
そしてその瞬間がやってきました。
掘削機の大きなモーター音のあと、地面からシュワシュワと
水が出てきました。目を大きく見張って、徐々に笑顔を見せて
くれる村の人たち。子どもたちの中には、歓声を上げ、手をた
たく姿も。乾いた地面がぬかるみ、水たまりができました。

写真13.14
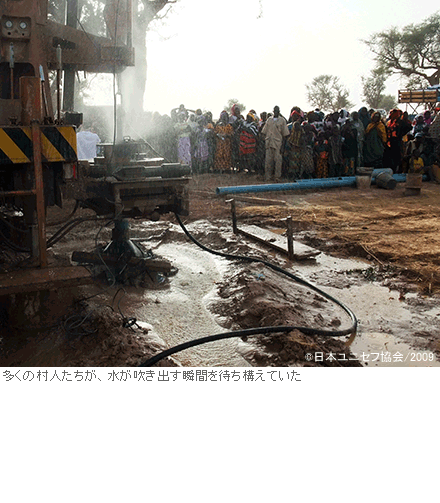
写真13.14
水が使えるようになれば、衛生的な生活が送れるようになり、
健康状況が改善されます。これまで使っていた泥まじりの水は、
家畜や農業に使えるようになります。水は、体だけでなく、生
活をうるおしていく、そういう変化をこの2年間見てきました。
チャアラ村にも、同じ変化が訪れるはず、そう信じて、村を後
にしました。
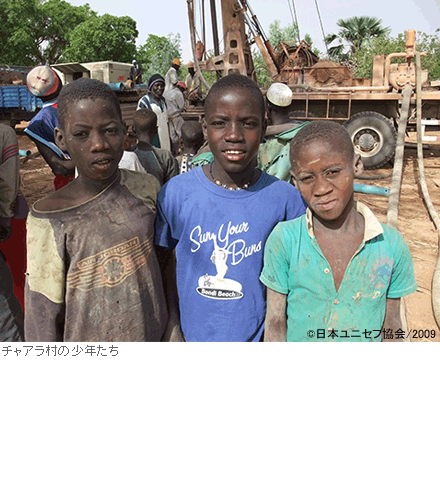
写真15
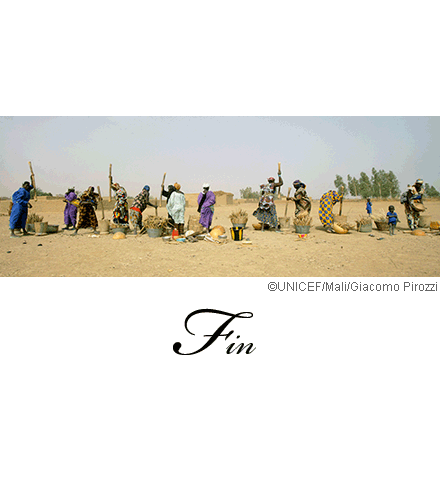
fin