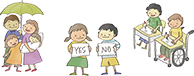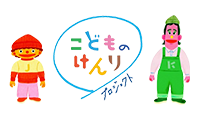南阿蘇村の子どもたち
ユニセフ授業にインターネットで参加
【2012年11月28日 東京発】
 |
| 南阿蘇の豊かな自然に囲まれた中松小学校 |
全国の学校への学習資料の定期的な配布や、巡回方式での"出前授業"の実施などを通じて展開する日本ユニセフ協会の"開発のための教育"活動。 この活動の一環として、ユニセフハウスと全国各地の学校の教室をインターネットで結び、チーム・ティーチング(Team Teaching=TT)方式の遠隔授業も実施しています。
2003年以来、「総合的な学習の時間」などを活用して年数回(校)、参加する子どもたちに、開発途上国の子どもたちが直面する問題や克服の為の取り組みなどを学ぶ機会を提供しているこのインターネットTT授業に、今月22日(木)、熊本県南阿蘇村立中松小学校の5・6年生の子どもたち33名が参加。アフリカの子どもたちが置かれている現状や、そうした状況の改善に取り組むユニセフ活動等について学ぶ機会を持ちました。
3回目の授業
 |
| 「今日学んだことを、是非、お友達や家族にも伝えてくださいね」。22日の授業には、最大10箇所の“中継”が可能なグーグル・ハングアウトの特性を活かし、スーダン・ダルフールでの勤務経験もあるユニセフ職員の斉藤洋之氏も、ユニセフ東京事務所から参加。世界的にも、最も厳しい状況に置かれているアフリカの子どもたちへの支援を訴えました。 |
中松小学校の子どもたちがユニセフのインターネットTT授業に参加したのは、これが3回目。最初のきっかけは、各県の教育委員会を通じて配付された、インターネットTT授業を紹介する日本ユニセフ協会の資料でした。
「長年、子どもたちは学校でお米を作って、あるNGOを通じて、アフリカのマリにそのお米を送ってきました。でも、子どもたちは、マリを遠い存在に思っていて、お米も、単なるプレゼントのようになってしまっていて、現実感がなくなっていました」と語るのは、5年生の担任の山下洋先生。「そこに、インターネットを使った授業の存在を知ったんです。ユニセフの方に、ここまで来ていただくのはなかなか難しいでしょうし」(山下先生)
"リアルな授業"
 |
| パワーポイントを使った「クイズ」や、アフリカの現状を伝えるインターネット動画など、次々と切り替わる画面を食い入るように見つめる中松小学校の子どもたち。メモをとり続ける子どもたちも。 |
今回の授業では、インターネット回線とパソコンで複数個所をつなぎ"テレビ会議"ができるグーグル社の製品「ハングアウト」を初めて利用。これまでのWEBカメラ1台だけの環境では難しかった、動画や写真・資料も画面上で共有され、より"リアルな授業"に近い形で授業が進められました。
山下先生も、紙の資料だけではなかなか伝わってこない内容が、インターネットを通じた(ユニセフやユニセフ協会の職員の)お話や、特に3回目となる今回の授業で初めて活用されたビデオなどによって、よりリアルに伝わってきたと語ります。
 |
| 「こうした授業が、簡単にできる時代になりました。他の学校の子どもたちにも、こうした機会がもっと広がるといいですね」と語る、中松小学校5年生の担任の山下洋先生 |
「自分たちが不思議に思っていたことを(今回の授業を通じて)たくさん知る事ができました。他の学校にも伝えていけるので嬉しいです」「私たちがやっている活動を、次の学年にも伝えていきたい」「作っているお米を販売する時に、今日習っていたことをチラシに書いて、地域の人たちにも伝えたい」 授業参加した子どもたちからは、こんな感想が寄せられました。
「子どもたちは、マリだけじゃなく、より広いアフリカの子どもたちが置かれている現状を、切実感を持って受け止めたようです。その切実感を、今後の学習でもっと深めていきたいと思います」「こうした授業が、簡単にできる時代になりました。他の学校の子どもたちにも、こうした機会がもっともっと広がるといいですね」(山下先生)
写真クレジット全て:©日本ユニセフ協会
* * *
日本ユニセフ協会では、この「TT授業」を、より多くの学校に活用していただきたいと考えております。実施に必要なインターネット環境など、お気軽にお問い合わせください。
【インターネットTT授業に関するお問い合わせ】
日本ユニセフ協会 学校事業部 (受付時間:9:00〜17:00 土日祝日休)
電話:03-5789-2014 FAX:03-5789-2034 E-mail:se-jcu@unicef.or.jp

|トップページへ|コーナートップへ戻る|先頭に戻る|
 寄付方法のご案内
寄付方法のご案内
 ご寄付による支援例・成果
ご寄付による支援例・成果
 領収書
領収書
 その他のご協力方法
その他のご協力方法
 個人のみなさま
個人のみなさま
 学校・園のみなさま
学校・園のみなさま
 大学生ボランティア
大学生ボランティア