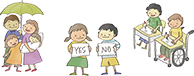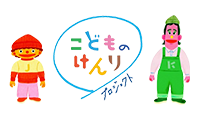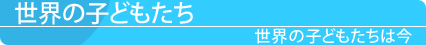
がんばれ先生!
<ラオス>
<2003年10月9日掲載>
ラオスのプホム村の先生はブンミ先生ただひとり。
ラオスのプホム村に赴任が決まったとき、ブンミ先生は妻とまだ手がかかる下の子4人を連れて、故郷の村シェンカイを後にしました。故郷とプホム村の間は12キロ。歩いて2時間半の道のり。それも山を登らないとたどり着けません。
この人里離れた、たった13家族しか住んでいない山間の村で、ブンミさんは子どもたちを教えています。学校に住み込み、村の子どもたち25人全員をひとりで教えています。学年は1年生から3年生。ひとつの教室で全員を教える複式学級です。
全学年が揃っていて5年生まで勉強できる学校は、一番近い所でもシェンカイまで行かないとありません。4年生以降も学校を続けたいプホムの子どもたちは、シェンカイの学校に通いますが、5日分の米を持って学校に出かけ、週末だけ家に帰ってきます。プホム村の人たちは親切で、ブンミ先生にも魚などを持ってきてお礼をしてくれますが、もう手はかからないとはいえ年上の子どもたちを故郷に残して、山里に住むのは辛い、とブンミさんは言います。
遠隔地の学校に勤める先生には臨機応変な知恵も必要です。教材も自由に手に入らないので、自分で教材を作らなければならないからです。黒板さえ、ありあわせの木を使って自分で作りました。それでもブンミ先生はひとりではありません。ユニセフが支援して開催されている教師のための技術向上研修で、社会的・専門的な支援を受けているからです。ブンミ先生は、この研修で、同じ境遇にある先生たちと相談し、経験を分かちあい、学校に必要な教材(紙そのほかの文具)をもって帰ることができるのです。
研修を1年続けてきたブンミ先生。教え方は確実に向上しています。特に複式学級をどのように教え、まとめていくか、そうした面で多くのことを学んだ、と言います。授業のヒントも得ることができたし、木の葉や穀物、果物から教材を作る方法も学びました。子どもたちは以前よりもきちんと学校に来るようになり、活発に、そして授業にも積極的に参加するようになったとも言います。以前よりも楽しそうだ、と。研修を受けた成果が着実に実を結んでいることが分かります。
研修では、ブンミ先生も同じような仲間たちと一緒に集うことができます。そして、研修が終われば、いろいろな教材を手に、前より自信を持って学校と村に帰って行くことができるのです。そう、この献身的な努力と犠牲が、決して無駄にならないことを知りながら…。
******************
ラオスには、教師研修を受けずに先生になった人がたくさんいます。特に遠隔地の学校の先生は資格もなく、研修も受けていないことが多いのです。それというのも資格を持つ先生は遠隔地の学校には赴任したがらないからです。1992年以来、ユニセフは、ラオス政府が行っている教師のための技術向上プログラム(Teacher
Upgrading Programme:TUP)を支援しています。このプログラムでは、先生たちが休暇を利用して2年にわたる研修を受けますが、その後1年、さらにTUPトレーナーによりモニタリングを受けます。この研修を終えると、先生たちは教員免許試験と、中等学校初級試験も受けることができるのです。
TUPは夏休み(6週間)と冬休み(2週間)の間に行われ、研修施設としては、その時々で用意できる教師研修大学、少数民族用の寮、中学校などを借りて行われます。各県で、約100〜140人の先生たちが毎年TUPに参加します。ユニセフは8つの県でTUPを支援し、そのほかの10の県では、別の団体が支援を行っています。
2003年度は、2週間の研修が2月に、6週間の研修が7〜8月に開かれ、計900人が研修を受けました。学校が始まってからは、TUPのトレーナーによってモニタリングが行われ、研修で学んだことが実際に学校現場で生かされていることが確認されるようになっています。
TUP参加者の選定にあたっては、いつもは正規の研修を受けることができない遠隔地の教師が研修を受けられるよう配慮がなされました。その結果、2003年には、全体で4分の1以上の参加者が少数民族の出身者となり、3県(ルアン・ナムサ、セコン、アタプー)では研修を受けた教師の51〜74%が少数民族の出身者でした。
こうした形で、教師の授業の進め方が改善されることで、特に遠隔地に住む子どもたちが、楽しく学校に通い、学べるようになることが期待されているのです。
2003年10月1日
ビエンチャン(ユニセフ)
注)TUPは、正規の学校に通った総合年数が8年未満の、教師研修を受けていない教師を対象に、県レベルで行われている事業である。こうした教師は小学校現場の教師の30%を占めている。このコースは、研修と教師資格試験を受けさせることで、教師の教育レベルを上げるのが目的で、研修やモニタリング支援を通して、教師たちの指導力の向上を目指したものである。コースの参加人数は一度に50人。夏季休暇を利用して6週間、冬季休暇を利用して2週間、連続2年間のコースという設定になっている。1992年以来、4,000人の教師がすでにこのコースを修了し、教師の資格を得ている。

|トップページへ|コーナートップへ戻る|先頭に戻る|
 寄付方法のご案内
寄付方法のご案内
 ご寄付による支援例・成果
ご寄付による支援例・成果
 領収書
領収書
 その他のご協力方法
その他のご協力方法
 個人のみなさま
個人のみなさま
 学校・園のみなさま
学校・園のみなさま
 大学生ボランティア
大学生ボランティア