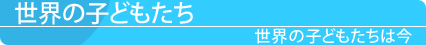
<2002年9月4日掲載>
〜サンクトペテルブルグのストリートチルドレン
ユニセフが支援する保護施設で「温かさ」を知る〜
<ロシア>
 サンクトペテルブルグ郊外、晴れわたった日曜の朝。13歳になるヴィトヤ・クレスチョフはじゃがいも畑の虫とりに必死です。つらい仕事ですが、じゃがいもの収穫を確実にするには大事なことなのです。ユニセフの支援を受けている保護施設「ライフ(生命)」で出る食事の主食はじゃがいも。つまり、みんなの食事がこの虫とりにかかっているのだといえます。実はいま夏休み中。サンクトペテルブルグから150キロ離れた、元軍の土地を使った畑で、こうしてほかの子どもたちと仕事をしているのです。朝、このように仕事をすること4時間。午後は泳いだり、釣りをして楽しみます。収穫できた物が、みんなの食卓に並ぶことになります。
サンクトペテルブルグ郊外、晴れわたった日曜の朝。13歳になるヴィトヤ・クレスチョフはじゃがいも畑の虫とりに必死です。つらい仕事ですが、じゃがいもの収穫を確実にするには大事なことなのです。ユニセフの支援を受けている保護施設「ライフ(生命)」で出る食事の主食はじゃがいも。つまり、みんなの食事がこの虫とりにかかっているのだといえます。実はいま夏休み中。サンクトペテルブルグから150キロ離れた、元軍の土地を使った畑で、こうしてほかの子どもたちと仕事をしているのです。朝、このように仕事をすること4時間。午後は泳いだり、釣りをして楽しみます。収穫できた物が、みんなの食卓に並ぶことになります。
保護施設には男女20人の子どもが住んでいます。ここは元劇場アーチストのエレナ・ククスチュキナさんが始めた施設です。「ライフ」はユニセフの長年のパートナーであるNGO"ドクターズ・オブ・ザ・ワールド"(アメリカの民間組織)からの財政支援で成り立っています。ユニセフとの合意のもとで、ドクターズ・オブ・ザ・ワールドは2人の医師、看護婦1人、ソーシャル・ワーカー1人の給料を支払い、子どもたちの基礎医薬品を提供しています。
「困っている子どもたちに何かしなければと思ったんです」とククスチュキナさん。「私自身はもう人生でいろいろ楽しんできたし、息子も大きくなって、私を道徳的にも財政的にも支えてくれる。でも、この子たちのことはいまのところ誰も面倒を見てあげられないの。いろいろな事情で親に見捨てられてしまったから」いろいろな事情の中には、アルコール中毒、ドラッグ(麻薬・薬物)、貧困、責任放棄などがあります。ソ連の崩壊とともにロシアが直面した経済的、社会的な変化の中で、多くの家族が困難に直面しているのです。「ライフ」ができてからというもの、すでに400人の男の子、女の子が支援を受けてきました。その1人がヴィトヤなのです。
ヴィトヤは7歳のときに家を逃げ出しました。両親はいつも泥酔状態でしたから、きっと彼がいなくなったことさえしばらくは分からなかったことでしょう。「家なんか大嫌いだった」とヴィトヤ。「ぼくと話してもくれないし、食べる物だってろくになかった。お金がなかったから学校にも行かせてもらえなかったし、勉強なんてどうでもいいって、ママは思っていたみたいだ」
彼が家を出たのは冬でした。
「ひとりで路上暮らしは怖くなかった?」
「家にいるよりずっと面白かったさ。ほかに3人の年上の子がいたし、地下の温かい場所にいたから、外がマイナス20度でも寒くなかった」とヴィトヤ。
「どうやって暮らしていたの?」
「人に物やお金をねだって生きてた。面白かったよ。食べ物は買えたし、ボンドを買うだけのお金も稼げたから。
ボンドは吸うために買うんだ。まあ、趣味のような生活で面白かったね」
苦しみと直面したくないストリートチルドレンたちは、往々にして、ボンドを吸って現実を忘れようとします。でも、これはほかのドラッグ(麻薬や薬)と同じくらい有害で、脳の細胞を急速に破壊して行きます。
 サンクトペテルブルグは500万の人口を抱えた大都市ですが、ストリートチルドレンが集まる場所は有名です。そこで、ヴィトヤの姉が彼を探し出し、家に連れ戻したことがあります。放蕩息子のご帰還を演出したつもりが、そうはいかず、ヴィトヤのお父さんはお酒に酔っ払って、また母親に暴力をふるい始めたのでした。それを見て、ヴィトヤはまた家を出ました。そして二度と帰ることはなかったのです。お姉さんもさすがに今度は追いかけてきませんでした。そう、どこにいるのかが分かっていても…。
サンクトペテルブルグは500万の人口を抱えた大都市ですが、ストリートチルドレンが集まる場所は有名です。そこで、ヴィトヤの姉が彼を探し出し、家に連れ戻したことがあります。放蕩息子のご帰還を演出したつもりが、そうはいかず、ヴィトヤのお父さんはお酒に酔っ払って、また母親に暴力をふるい始めたのでした。それを見て、ヴィトヤはまた家を出ました。そして二度と帰ることはなかったのです。お姉さんもさすがに今度は追いかけてきませんでした。そう、どこにいるのかが分かっていても…。
ヴィトヤは路上で物やお金をねだって生活を続け、ボンドを吸う毎日が続きました。こんな生活が続くこと1年。あるとき別の子が衣類を提供してくれる保護施設について話してくれました。ぼろぼろになったズボン姿で、ヴィトヤはそこを訪れました。そのとき、彼はまだ8歳。
「彼ら(ソーシャル・ワーカー)はぼくが持っていたボンドを取り上げたんだ」ヴィトヤはふりかえって言います。「めちゃくちゃ頭に来た。でも、食事ももらえたし、なんとなく居心地が良かったので、いることにしたんだ。でも、それが正解だったみたいだ」
 これは5年前のこと。「路上で生活していたら、きっと死んでいたね」ヴィトヤはいま正規の学校に通い、がんばって勉強をしています。得意な科目は体育。磁器の花瓶やロウソクを作るのも得意。昨年のクリスマスには手作りのナフキンを売って、いくらかのお金を得ることもできました。「手作りの品を売って、そのお金で保護施設に敷くカーペットを買うことにしたんだ」彼は言います。「で、実際に買ったよ! どれだけ感激したか分からないだろう? 家のあたたかさを感じられて…自分の本当の家ではないんだけれど、そういうあたたかさが感じられるのは本当にうれしい」
これは5年前のこと。「路上で生活していたら、きっと死んでいたね」ヴィトヤはいま正規の学校に通い、がんばって勉強をしています。得意な科目は体育。磁器の花瓶やロウソクを作るのも得意。昨年のクリスマスには手作りのナフキンを売って、いくらかのお金を得ることもできました。「手作りの品を売って、そのお金で保護施設に敷くカーペットを買うことにしたんだ」彼は言います。「で、実際に買ったよ! どれだけ感激したか分からないだろう? 家のあたたかさを感じられて…自分の本当の家ではないんだけれど、そういうあたたかさが感じられるのは本当にうれしい」
ヴィトヤはアルコール中毒の家族と過ごした日々、そしてストリートチルドレンとして路上で過ごした日々を取り戻すことはできません。両親もいまどこにいるか分かりません。父親は一度施設を訪れ、彼に40ルーブル(およそ150円)を置いて行きましたが、一家が住む住所は残して行きませんでした。
「お母さんが恋しい」ヴィトヤは小さな声で言います。「5年も会っていないんだから。会えたらいいな。でも、この施設でも充分幸せさ。路上に戻るなんて想像もできないよ」
サンクトペテルブルグ、ロシア 20-8-2002 UNIICEF
アンナ・チェルニャコフスカヤ、ユニセフ広報官

|トップページへ|コーナートップへ戻る|先頭に戻る|

