
報告会レポート
ユニセフ50周年記念行事
「ユニセフ子どもの祭典」に参加して
■(財)日本ユニセフ協会創立50周年記念行事「ユニセフ 子どもの祭典」 |
■2005年5月1日13:00〜17:15@両国国技館 |
 この度は、ユニセフ50周年記念行事「子どもの祭典」に参加させていただき、ありがとうございました。参加したJCVの学生メンバーが、後にメールでそれぞれの意見や感想を交換しました。以下はそのやりとりの内容をまとめたものです。
この度は、ユニセフ50周年記念行事「子どもの祭典」に参加させていただき、ありがとうございました。参加したJCVの学生メンバーが、後にメールでそれぞれの意見や感想を交換しました。以下はそのやりとりの内容をまとめたものです。
◆内藤明日香(17歳)
アフリカの現状などを改めて知り、あまりにも大きすぎる話のように感じてしまい ここにいる限り何もできないのではないか、これから先何も変わらないのではないかと思ってしまう部分もありました。しかし、このような祭典があり、そこに人が集まり、議論しあい、世界について考える。これは決して絶望的なことではないと、同時に希望も持てました。また、パネリストとして参加していたユニセフ子どもネットワーカーのお二人が高校生ということもあり、とても勇気付けられました。
難民問題には特に関心があるのですが、いろいろなことを知るたびに子どもたちを取り巻く悪循環に対して、どうして、とつらい思いでいっぱいになります。
私よりも幼い子どもが当たり前のように銃を持ち人を殺すことを強要される、家も家族もすべて焼き払われ、幼い兄弟を抱えながら難民キャンプに子どもが助けを求めてやってくる。このような世界があるのは事実であり、私はそのような人々に対してこれは正常ではない、人が争わない世界がこの世にあるのだということを強く伝えたいと思いました。このような現状にありながらもかわいらしい笑顔で写真におさめられている子どもたちを見て、どうして何もせずにいられるのでしょうか?
◆園田有香(19歳)
UNICEF、シンポジウムで最初に印象的だったのは、やはりその組織の大きさでした。組織ががっちりとしているその分全体がよく見えない、という部分も率直に言うと残りました。まだまだこれから問題が進行形という事からグローバル化の負の側面はもっと深く調べたいキーワードです。日本(ツアーなどを通して)が加害者になる事、それを自覚した上でミャンマーを見つめようとも思いました。募金でもボランティアでもまさか与える側、という視点だけであるのは何か違う、と改めて思いました。先のアンジェリーナ・ジョリーの話にも出て来たシエラレオネの話はUNICEFのシンポジウム中ずっと頭にちらついていました。まさに『大人の事情』でボロボロになってしまった子供達の話は、そしてこれが現実にこの地球上にある事なんだ、という事は衝撃と共に絶望感すら感じた事でした。けどこんな事を頭に残しつつ、まだお役に立てていませんが、ワクチンの事務所で活動していきたいと思います。
◆江崎景介(10歳)
ユニセフの話を聞いてアフリカの子どもたちがたくさん殺されてかわいそうだと思いました。それで400円のお小遣いのうち100円を募金しました。
◆江崎智奈美(15歳)
講演などを聞いて私は世界の子ども達の様子はだいたいわかっていたのですが、今回色々な専門家の方たちの『何が原因で私たちには何が出来るのか、またメディアが出来ることはなにか』などいろいろな面からの話がとても耳に残っています。この話を聞いて私は今まで自分に出来ることは何かということばかり考えることが多かったので今まで考えたこともなかった『メディアが出来ることはなにか』という話にとても興味を持ちました。
シンポジウムでパネラーをしていたユニセフ子どもネットワーカーの高校生はNPOを立ち上げたという望月君は凄いと思ったが、日本の高校生の代表なのにも関らず発言がちょっと曖昧だったと思う。『戦争をしている人はいじめっ子が弱いものいじめをしているのと同じことだ』と品川さんは言っていたが、私はちょっと違うと思いました。戦争とはそんな単純なことではないと思います。
今回ユニセフ祭典に行っていろいろなことが学べました。皇太子殿下にも逢え てよかったです。
◆小暮倫子(19歳)
ユニセフ協会を立ち上げた世代の人々が、戦後の日本が国連ユニセフから受けた脱脂粉乳に対する感謝の気持ちをいかに強く持っているかを感じた。私たち若い世代は、経済的に発展し豊かになった日本に生まれ、物質的に見れば「与える側」の立場しか知らないが、そうした年配の方々の話を聞くことによって、私たち人類は助け合って生きていくものなのだということを学ぶことができ、またその精神を受け継いでいかなければならないのだということを感じた。
アグネス・チャンからのスーダンの報告、シャラッド・サプラ氏のアフガニスタンの報告も、この上なく悲惨な内容。でも、平野氏が言っていたように、それに目をそむけるのではなく、現実として受け止めるところからはじめなければならない。そして問題解決のためには、品川さんが悔しいといっていたけれど、一人では人間なにもできなくて、いろいろな方面の人々がいろいろなアプローチで、様々な切り口でかつ協力して取り組まなければならない。それはメディアであったり、旅行会社であったり、ユニセフであったり、UNHCRであったり、ユネスコであったり、JCVであったりもするわけだ。JCVの活動はこの世界をよりよくする活動のわずかな一部でしかないけれど、たしかに一部であるのだから、これからもその一員として頑張りたい。
「世界の子どもにワクチンを」日本委員会
編集担当 学校事業部 小暮倫子

|トップページへ|コーナートップへ戻る|先頭に戻る|
 寄付方法のご案内
寄付方法のご案内
 ご寄付による支援例・成果
ご寄付による支援例・成果
 領収書
領収書
 その他のご協力方法
その他のご協力方法
 個人のみなさま
個人のみなさま
 学校・園のみなさま
学校・園のみなさま
 大学生ボランティア
大学生ボランティア











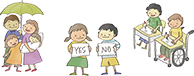
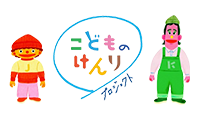




 この度は、ユニセフ50周年記念行事「子どもの祭典」に参加させていただき、ありがとうございました。参加したJCVの学生メンバーが、後にメールでそれぞれの意見や感想を交換しました。以下はそのやりとりの内容をまとめたものです。
この度は、ユニセフ50周年記念行事「子どもの祭典」に参加させていただき、ありがとうございました。参加したJCVの学生メンバーが、後にメールでそれぞれの意見や感想を交換しました。以下はそのやりとりの内容をまとめたものです。 