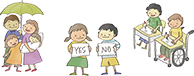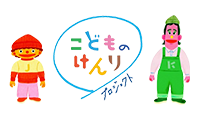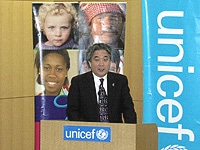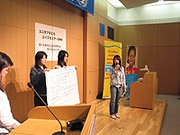報告会レポート
ユニセフ子どもエイズセミナー2006春
ぼくたちわたしたちが考える子どもとエイズのこと
■ 日時: 2006年3月31日(金)10:30〜16:30
■ 場所: 東京・港区高輪 ユニセフハウス
■ 主催:(財)日本ユニセフ協会
| ■ 司会: |
中津川有紀さん(子どもネットワーカーOG)
藤原美典さん(子どもネットワーカーOG) |
| ■ スペシャルゲスト: |
ナブケニャ・リタ・ブケンヤさん(ウガンダ)
アグネス・チャン日本ユニセフ協会大使 |
いまHIV/エイズは、世界の子どもたちにとって深刻な問題になっています。HIVウイルスに感染している子どもは世界で220万人。さらに、毎日6000人の若者が新たに感染しているといわれています。そのエイズについてともに学び、考えようと、日本の子どもたち約70名が集い、ユニセフ子どもエイズセミナーが開催されました。
特別ゲスト、ナブケニャ・リタ・ブケンヤさん(ウガンダ)のお話と、HIV/エイズと子どもに関するユニセフの取り組みを学んだ午前中の全体イベントに引き続き、午後はふれあいコースとおしゃべりコースの2コースに分かれてグループワーク。ふれあいコースではHIV/エイズの影響を受けている子どもをテーマに劇をつくり、おしゃべりコースではHIV/エイズ・タブー視の問題について、子どもたちが話し合いをしました。
■ プログラム
はじめに−HIV/エイズとは
HIVはウイルスの名前で、ヒト免疫不全ウイルスといいます。エイズとは後天性免疫不全症候群の略で、自分の体を病気などから守る免疫力をなくしてしまう病気です。現在、HIVに感染している人は世界に約4,200万人以上、そのうち子どもは220万人といわれています。まだ完全にこの病気を治す方法はなく、特に開発途上国では高い薬代を払える人が少ないため、ウイルスに感染した人は早くにエイズで亡くなってしまうことが多くあります。15〜24歳の若者への感染は毎日6,000人。エイズで親を失った子どもは1,500万人にのぼります。
HIV/エイズは血液や体液を通じて感染する病気で、だれでもかかり得るものですが、握手をしたりお風呂に入ったりなどの普通の生活では決してうつりません。しかし、エチオピアやその他一部の国や地域では、エイズや性ついて話すことはタブー視され、感染者は差別の対象になることから、地域の人や家族、子どもにさえ自分の病気を話せない人がいます。
リタさんのお話
HIV/エイズについての話を皆さんの前でするのは初めてです。ウガンダではふつう、学校でビデオを観たり、一般的な常識としてHIV/エイズの話を聞くことはありますが、個人的な体験については公に話すことはあまりありません。
ウガンダはアフリカの東部にある、小さな内陸国です。ヴィクトリア湖という大きな湖がありますが、海には面していません。雨季と乾季の2つの季節があります。首都はカンパラ。日本の3分の2の広さの国土に、東京の2倍の人口が暮らしています。普通に話されている言葉は英語ですが、その他にもいろいろな言葉が話されています。
ウガンダの子どもたちは、5歳くらいでも、HIV/エイズについて詳しいことは知りませんが、少なくともエイズという言葉は知っています。学校ではビデオを見せられたり、エイズにかかったらどういったことが起こるかということをしっかり教えてくれます。また、小学校や中学・高校では、HIVの感染予防法などの情報が載っている新聞が無料で配られています。そのほかにラジオ局もあり、子どもたちがHIV/エイズについて話をする番組もあります。このようにHIV/エイズについて学び、知識としては持っていながら、それを無視する人もいます。
私の父親は、7歳のときにエイズで亡くなりました。ですが、父が亡くなったときは、その理由を教えてもらえませんでした。亡くなる前は、病院に出たり入ったりして、仕事に復帰することができるぐらい元気に回復していた時期もありました。ウガンダでは女性はあまり外では働かず、私の母も仕事はしていませんでした。私の家は、父親の仕事で家計がもっていたのです。そのため、父親が死んでから家計は苦しくなりました。そのとき母親から、父がエイズで亡くなったことを聞かされたのです。私はすごくショックを受けて、悲しくなりました。
父が亡くなってから母が働きはじめましたが、なかなか多くは稼げません。そのため、だんだん学費が払えなくなり、学校を休むようになりました。母は、昼も夜も必死に働いて子どもたちを支えてくれました。学費が払えなくなり、校長先生にお母さんのほうから続けさせてくださいとお願いにいったこともあります。ここまでならと校長先生が言った費用も払えなかったときも、母は教育を続けられるように一生懸命いろいろな策を練ってくれました。私自身、いろいろつらい目にも遭いましたが、教育はこのまま続けなければいけないと自分を励ましました。
学校には私と同じような境遇の子どももいました。その中には、学校をやめてちょっとした仕事についたり、結婚の道を選ぶ女の子もいました。ハウスヘルパーという、ほかの家にそれで住み込みで働く道を選ぶ女の子もいます。ですが、ハウスヘルパーの雇い主は、家庭内労働の子どもたちに対する扱いが非常に乱暴です。
高校卒業後、奨学金を得ることもできず、私はしばらく家で何もせずに過ごしていました。大学に進学した友だちが家に遊びに来ていろいろ大学の話をしてくれましたが、本当は会いたくありませんでした。もしお父さんが生きていたなら同じように大学に通えたかもしれないのにと、とても寂しくて、また、反面とても恥ずかしかったからです。
ウガンダの子どもは、中学校などで外国語を学ぶチャンスがありますが、私の場合はそのような機会がありませんでした。そこで、少なくとも外国語をひとつ身につけたいと考え、高校を卒業してから約1年後にウガンダにあるあしなが育英会のレインボーハウスに通うようになり、日本語を学び始めました。
レインボーハウスに通い出してからしばらくすると、ある日本人スタッフから早稲田大学受験を勧められました。書類審査、日本での面接試験を経て、合格というニュースを聞いたのは2006年1月のことです。日本という遠い国に来れるなんて、とてもうれしくて躍り上がりたい気分でした。日本に来たときには、本当に美しい国で感激しました。
今後は国際関係と権利を学び、子どもの権利保護の分野に進みたいと思います。カウンセリングを通して、HIV/エイズの予防法やエイズに関する問題を解決していく方法を見出していきたい。それというのも、カウンセリングを通して自分自身が救われたという個人的な経験があるからです。
本日は、HIV/エイズについてこのようにお話をさせていただき、ありがとうございます。私の個人的な経験を通して、皆さんが何かしら学んでいただければ幸いです。
リタさんへの質問
Q エイズにかかっている子どもは周りにいませんでしたか?
A 日本の場合でも同じだと思いますが、恥ずかしいことと思われていますし、公表することによって周囲からいろいろ言われるため、公に自分からは言えません。お父さんお母さんがエイズで死んだこともいえません。うわさなどでわかる程度です。
Q お父さんが亡くなったとき、周りはどのような反応でしたか?
A 父が亡くなったときにはまだとても小さかったため、よく覚えていませんが、一般的に、人が長く患ってから亡くなると、エイズに間違いないと皆さん推測をします。これほどエイズが蔓延しているから、きっとエイズに違いない、と考える人が多いと思います。
|先頭に戻る|
エイズと子どもたちに関わるユニセフの取り組みについて
−早水研 日本ユニセフ協会専務理事
エイズについてはしっかりした理解を持つことがとても大切です。ユニセフも、子どもたちや若者を含む、あらゆる年齢層の人々に知識を持ってもらう活動に取り組んでいます。きょうは、2003年に訪れたスワジランドという人口100万人ほどの小さな国の話をします。
スワジランドはウガンダよりもHIV/エイズの有病率が高い国で、おとなから子どもまで含め、人口の35%ほどがHIVに感染しています。そのため、教育や水と衛生、子どもの保護など、いろいろな分野のユニセフのプログラムのすべてにおいてHIV/エイズが中心に据えられています。
ユニセフのエイズと子どもたちの問題に対する取り組みは大きく4つに分かれます。そのうちの1つが、母子感染という、母親から子どもへのHIV感染です。母子感染を防ぐために大事なのが、妊娠中の女性がHIVに感染していないかどうかを調べること。そして感染していた場合は、子どもにうつさないように適切な措置をとることです。
現在220万人の子どもがHIVに感染しています。そして毎年約50万人の15歳以下の子どもがエイズで亡くなっています。その大半は、生まれるとき、もしくはその後に、母親からHIVに感染した子どもです。すなわち、母子感染を防ぐことで、15歳以下の子どもの死の大半を防ぐことができるのです。
現在では、母子感染はほぼ確実に防ぐことができます。母親がHIVに感染していた場合、適切な措置をとらないと生まれてくる子どもの3人に1人ぐらいがHIVに感染してしまいます。ですが、適切な母子感染予防策をとることによって、感染率を2%以下に下げることができます。先進国であれば帝王切開と呼ばれる手術で子どもを産み、感染をほぼ間違いなく回避できる方法もあります。ですから、母親が、自分が感染しているかどうかを知ることがとても大切なのです。
エイズの影響を一番受けているのは、一番働き盛りのおとなです。父親や母親、学校の先生やお医者さん、農業や工場で働く人、警察官などといったおとなたちが一番激しくその影響を受けているのす。その結果、リタさんと同じように、親をエイズで失ってしまった子どもたちの面倒をみる家族をどのように支えていくか、ということが大きな問題になっています。
お父さんお母さんが亡くなると、おじいさんやおばあさんなどの親戚の人がまず助けてくれます。ところが、これだけエイズが広まり、子どもを持つおとながみんな死んでしまうと、これ以上親戚の子を育てることができない、ということになってしまいます。子どもがある程度大きければ子ども自身が働いて家計を助けることもできますが、小さい子だけが後に残された場合にはそういうわけにもいきません。ですから、小さな子を引き取ることが本当に大変なことになってきているのです。
そうした子どもたちは学費が払えずに学校をやめざるを得なくなったり、働きに行かざるを得なくなる。住み込みのお手伝いとして、全く知らない人の家庭の中で働かなければいけない場合もあります。すると、非常に虐待されやすく、場合によっては性的な虐待も起こります。そして、そこでまた若い子どもたちにエイズがうつるということも起こります。ですから、子どもたちを保護する環境をどのように維持するかということがとても大事なことになっています。
その取り組みのひとつとして、ユニセフは、子どもたちが何とか生きていくために、最低限の食事を提供するお手伝いをしています。親が亡くなり子どもたちだけで暮らしている子どもは、食糧もなかなか手に入らず、非常に厳しい生活をしています。そこで村の教会に女性が集まり、子どもたちに1日1回、温かい食事を提供するのです。ユニセフはここで調理道具を提供しています。
もうひとつの取り組みは、エイズで親を失った子どもが、学校に来られるようにする取り組みです。そのために、学校の中に、1人の子どもに一区画の畑を与え、野菜を育てさせます。子どもが面倒をみなくなるとその区画の野菜がしおれてしまうため、子どもが学校に来ていないということがわかるのです。野菜の栽培方法を学ぶこともできると同時に、採れた野菜を含めることによって栄養のバランスの取れた食事を摂ることもできます。またコミュニティの菜園では、世界食糧機構(FAO)が開発した、先進的な野菜の栽培方法をおとなに教えています。
スワジランドでは学校制服がありますが、これをやめ、制服にかかる費用を免除することによって、子どもが学校に行きやすくするという取り組みも始めました。以上のような形で子どもを学校に通わせ、コミュニティ・センターとしての役割を通じて食事を提供し、かつ最先端の技術を使った農業も伝え、子どもたちが健全に育つような環境をつくるという活動をユニセフは行っています。このほかにも、子どもや若者自身によるHIV/エイズの啓蒙活動や、若者によるコミュニティの子どもたちへの食糧・農作物の提供も行われていました。
エイズに対する取り組みは、何かひとつやればいいということではありません。まず自分を守るところから始め、拡大家族やコミュニティ、政府も含めた国全体として取り組みを立ち上げて、強化、広めていくために、ユニセフは政府やコミュニティ、学校、教会など、みんな一緒に頑張るように働きかけて活動しています。
早水さんへの質問
Q アジアではHIV感染は広まっているんですか?
A アジアでは広がっているところと、抑え込みに成功しつつあるといわれるところに分かれています。タイやカンボジアに加え、ミャンマーなども感染率が高くなりつつあります。またインド、中国という非常に人口の大きな国で、エイズが大きな問題になりつつあります。世界全体のHIV感染者4,200万人のうちの約2,800万人ぐらいがアフリカですが、アジアについても今後注意が必要です。
|先頭に戻る|
■ 午後の部
ふれあいコース発表
ふれあいチームでは、あるエイズによる孤児の女の子の話をみんなで読み、それをもとに登場人物の気持ちを考え、劇をつくりました。もうひとつのふれあいグループでは、同じ話をもとに、主人公の女の子が成長して先生になるところまでをつくりました。
おしゃべりコース発表
おしゃべりコースでは、まず中学生の意見や文部科学省の見解、さまざまなメディアの情報などを集めた資料集を読み、自分の体験や経験を踏まえて話し合いをしました。話し合いのテーマは「なぜ多くの日本の若者はHIV/エイズの問題をタブー視する傾向があるのか」。これにそって5つの設問を用意し、話し合いました。
| 設問1: |
HIV/エイズタブー視の問題点は何か? |
| 設問2: |
タブー視の原因、理由はどこにあるのか? |
| 設問3: |
タブー視の問題、HIV/エイズ全般の問題を解決していくには何をすればよいか?私たちや政府、メディアなどはどういうことをすればよいのか? |
| 設問4: |
設問3で出た解決策に取り組むにあたり、課題・問題は何か? |
| 設問5: |
設問1から4まで考えた結果、どのような考えを持ったか? |
■ 設問1: HIV/エイズタブー視の問題点は何か?
HIV/エイズについて話すのが恥ずかしい。日本の文化、社会、自分の意見表現を抑える。知らないということが感染を広げる。話をするきっかけがあまりない。
■ 設問2: タブー視の原因、理由はどこにあるのか?
エイズについて日本人全体が定着したイメージを持っていること、学校などで教える教育の格差、教育委員会の意識、身近にHIV感染者がいないために受けとめられない、メディアによる報道の仕方などが問題だと思う。HIV感染者をどう受けとめればいいのか、ということをまず考えたほうがよい。
■ 設問3: タブー視の問題、HIV/エイズ全般の問題を解決していくには何をすればよいか?私たちや政府、メディアなどはどういうことをすればよいのか?
- 教育では、ビデオを見せたり、お薦めの本を紹介するなど、先生によって内容が変わることのない、統一した教育を提供する。
- 小学生のときからエイズや保健に関することをもう少し詳しく教える。
- 中学生ぐらいになると、恥ずかしかったり話しにくかったりするので、男女別のディべート形式にする。
- 市役所や保健所にエイズの相談窓口や検査施設を設け、広報紙やインターネットに載せるなどして身近なものにする。
- アーティストや芸能人に参加してもらい、たくさんの人に関心を持ってもらう。
- リストバンドやストラップなど、ふだん私たちが使っているものや興味があるものに関連づける。
- 政府の省庁で意見を統一する。
- エイズ検査薬をコンビニなど、手軽に入手できるようにする。
- 教育や政府の責任ばかり追及するのではなく、自ら知識や情報を集める姿勢を持つ。
- 情報を受信するだけではなく、友達や親に話したり、小さい話し合いの場を設けるなど、発信していく立場に立つ。
■ 設問4: 設問3で出た解決策に取り組むにあたり、課題となる問題は何か?
- 教育の統一
学校教育の場合には時間の有無が課題になると思う。例えば公立の学校では、政府の出したカリキュラムによって授業が行われ時間が確保できないため、カリキュラムを組み直す必要が出てくる。カリキュラムを組み直すときも、世論の総意や、それを組み直す時間がかかる。結果として、進行が遅れるという課題も生まれる。
- 役所などに窓口を設ける
日本全国の役所に、カウンセラーや専門家を配置できるほど、人の数が揃っていないという現状がある。そして、全国的にHIV感染者などの貴重な体験を話す場があまりない。
- 検査薬の市販化
エイズ検査を身近な健康診断の場に取り入れる。
通信販売やドラッグストア、薬局で入手できるようにする。課題、店頭で購入する際の店員の反応など、偏見を取り除く。
■ 設問5: 設問1から4まで考えた結果、どういう考えを持ったか?
今回話し合うことによって、他人事ではなく、自分のことのように考えることができた。HIVに限らず、1人ひとりの人間が意識することによって社会の感覚は変わるので、タブー視なども同じようになくなっていけばいい。タブー視をなくすには、まずHIVについて知ることが大切。きょうの参加者は正しい知識を知ることができたと思うので、これからは自分からも発信し、知識を広めてほしい。
|先頭に戻る|
アグネス・チャン日本ユニセフ協会大使
ユニセフがなぜHIV/エイズの問題に力を入れて取り組むか、それはこの問題はおとなの問題だけではなく、今や子どもの問題だからです。1つは母子感染の問題。HIVウイルスを抱えている母親は、妊娠すると、子どもを産むときに気をつけないと子どもが感染してしまうのです。
HIV/エイズは、ほかの病気と違い、ウイルスが自分の体に入っていても発病するまで何にもわからず、自分の感染を知らない人はどんどん人にうつしてしまいます。HIV/エイズは働き盛りの一番生産力を持っている人たちの命を次々と奪いつづけ、自分の面倒を見ることのできない弱いものが残されるのです。
いま1,500万人の子どもたちがエイズによって親を亡くしています。アフリカの国々では、子どもが親を亡くしたら、ほかの親が子どもの面倒を見ます。ですが、エイズによる孤児の場合は、必ずしも受け入れ先があるとは限らず、アフリカの社会の中でも面倒を見てもらえない子どもたちが増えています。そこで保護施設などでは、子どもに生活力をつけさせるよう取り組みを行っています。ですが、必ずしも子どもがみなセンターにたどり着くわけではありません。親を亡くして、さらに自分が病気を発病して死んでしまう子どももいます。薬を飲ませてあげればいいのですが、現地の人々にとっては手の届かない値段です。私たちが募金して支援することが、いまできることのひとつなのです。
また、予防も大切です。いろいろなキャンペーンを通じて、子どもたちから子どもたちへ知識を伝えることが大切です。子ども同士で自分たちを守り合うのです。
HIV/エイズの問題は、逃げたら消えるものではありません。私たちは勇気を持ってこの問題と向き合い、自分の問題として考えなければなりません。
こんどレソトへ行って子どもたちと会い、その子どもたちの状況をまた皆さんにお伝えしたいと思います。皆さんも、また1人ひとりが自分の友だちなどにきょうのことを伝え、その友だちがまたその友だちに伝えていけば、知識がどんどん広がっていきます。子どもたちが本当に一生懸命生きようとしていることを、私たちは忘れてはいけないと思います。
閉会の言葉(早水専務理事の言葉)
いろいろな人にとって、きょうは初めての話だったり、ちょっとショックだったり、いろいろな思いを持ったと思います。ですが、こういうことを知らないと、世の中のことはわからないし、ほかの国の子どもたちがどういう思いで生活しているのかということもわかりません。どうか、きょう学んだことを含めていろいろな人と話し合ってください。それによって、みんなでこの地球がもっとよくなっていきます。きょうみんなと勉強し、友だちになった中で感じたこと、思ったことを大事にして、明日からまたほかの人たちと仲よく、世界の子どもたちのために行動することを考えてください。
写真:(C)日本ユニセフ協会

|トップページへ|コーナートップへ戻る|先頭に戻る|
 寄付方法のご案内
寄付方法のご案内
 ご寄付による支援例・成果
ご寄付による支援例・成果
 領収書
領収書
 その他のご協力方法
その他のご協力方法
 個人のみなさま
個人のみなさま
 学校・園のみなさま
学校・園のみなさま
 大学生ボランティア
大学生ボランティア