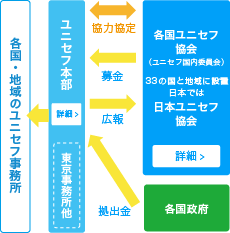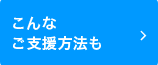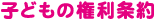|
HOME > ニュースバックナンバー2015年 >
|
|
|
|
|
 |
| © UNICEF Somalia/2014/Abshir |
| ユニセフが支援するセンターで新しい技術を身につける、元子ども兵士。 |
「バシルはAMISOMに2カ月拘束されました。まるで刑務所のようなところでした。バシルが生きているのかも、そこで何が起こっているかも、全く分かりませんでした」
バシルくんはその後、ユニセフが実施するカウンセリングや社会復帰プログラムに参加することになりました。社会復帰プログラムを運営するユニセフのパートナー団体は、バシルくんは一時ケアセンターに入り、カウンセリングを受けた後、教育や職業訓練プログラムに参加する必要があることをカドラさんに説明しました。
カドラさんは、バシルくんは全く別人のようになってしまったといいます。
「武装グループに入る前とは、まるで別人のようでした。ショックを受け、トラウマを抱えていました。最近の様子を聞いても、『元気だよ』と言うだけで、それ以上話そうとはしませんでした」
バシルくんは7カ月の間、一時ケアセンターで過ごし、戦闘に参加した際に負った目の傷の手術も受けました。バシルくんは依然として武装グループでの経験について固く口を閉ざしたままです。カドラさんは、このプログラムでバシルくんが再びよい人生を歩むことができるようになることを望んでいます。
「今でも、武装勢力での経験を話そうとはしません。でも、今は前のように幸せそうな姿を見せますし、会話もするようになっています。バシルは学ぶことの大切さを理解しました。とてもよいプログラムだと思います。このようなプログラムなしでは、武装勢力にいた子どもたちはトラブルを起こしてしまいますから」
カドラさんは、バシルくんの将来のためには教育を続けることが唯一の道だといいます。
「武装グループからまた誘われる危険は、まだあります。でも、バシルは読み書きもできるようになり、いろいろなことを理解できるようになりました。もう、武装グループには興味を持っていません。今はとても幸せそうです。参加しているプログラムの内容や、将来の夢について教えてくれるのです」
1.戦闘でトラウマを負った、元子ども兵士 バジルくん(16歳)
身長170cmほどで華奢な体つきのバシルくん。笑顔が素敵で、探究心のある目をしています。話しかけると目を合わせてくれますが、そのほかは自分の手や遠くを見つめ、常に周りにあるものを触っています。問いかけにはにこりと笑い、冷静に答えます。
バシルくんは友達に勧められるまま、14歳で故郷の小さな町を飛び出し、武装グループに加わりました。
「学校の友達は、武装グループに入るのが一番だと言っていたので、ぼくも参加することにしました。これで全てうまくいくと思いましたが、悪い結果に終わりました。銃や戦闘だらけの日々でした」
自分の行方は近所の人たちを通じて家族に伝わるため、家を出てからはほとんど家族と話すことはなかった、とバシルくんは言います。
バシルくんは、武装グループでの具体的な役割や行動の質問には答えようとはしません。他の子どもたちのように、「歩兵だった」と言うだけです。
「ぼくよりも幼い子どもたちをたくさん見ました」と、バシルくんは続けます。かつて、子どもたちは倒れた兵士から武器を奪って修理をしたり、使用人や”人間の壁”などの役割を命じられていました。バシルくんの片目や足に残った多くの銃弾による傷は、AMISOMとの戦闘に初めて参加した時のものだといいます。
「初めて戦闘に参加したときは、撃たれてしまうのではないかという恐怖でいっぱいでした」と、バシルくんが話します。2012年、2度目の戦闘の際にバシルくんは拘束されたといいます。
「あれは木曜日の、雨が降っている朝でした。目を覚ましたばかりで、闘う準備はできていませんでした。AMISOMが突入してきて、逃げた人たちは捕まりました」
戦闘が激化し、逃れることができたのはわずか一握りでした。バシルくんは、他の人たちが殺されていく様子を目にしていました。
「5人の友達が死にました。3人は、ぼくの目の前で殺されました」と、低い声で、落ち着かない様子で椅子を何度も座りなおしながらバシルくんが話します。「とても怖かったです。ショックでした。今でも眠っている時、その時の様子がよみがえってくる悪夢を見ます」
バシルくんはAMISOMに拘束され、軍の収容所に連れていかれました。それから、ユニセフにより、バシルくんはパートナー団体によって運営されている一時ケアセンターに身を置くようになりました。これは、武装勢力やグループと関わる子どもたちのためのユニセフの社会復帰プロジェクトの一環として行われています。
「カウンセラーに、どんなことでも話すように言われました。カウンセリングは楽しかったです」と、満面の笑みでバシルくんが話します。
7カ月にわたるカウンセリングと、足に残っていた爆弾の金属片の摘出手術を終え、バシルくんは叔母さんのもとに引っ越し、一時ケアセンターで教育や職業訓練を開始しました。傷を負いほとんど視力を失っていた片目の手術を受けることもできました。
地域のために働きたいというバシルくんは現在、電気工学を学んでいます。バシルくんの夢は、モガディシュで電化製品を扱う店を開くことです。
2.女性初のレストラン経営者を目指す、ハリマさん(18歳)
ハリマさんは15歳のときに年上の男性と結婚し、ふたりの子どもを授かりました。しかし、ある日、夫は娘と息子を連れて姿を消し、戻ってくることはありませんでした。
「夫はふたりの子どもを連れて出て行ってしまいました。もし追いかけてきたら、命はないと脅されました」ハリマさんは両親とモガディシュにある国内避難民キャンプに身を寄せており、夫が武装グループで技術者として働いていると避難先で耳にしました。
「電話をかけたこともありました。でも、電話をかけ続けるなら殺すと言われました。夫はわたしを悲しませて電話をかけるのを止めさせるために、子どもは死んだと嘘をついたこともありました」
「叔父が子どもたちの無事を確認してくれました」その時のことを思い出して、ハリマさんが震えながら話を続けます。「2カ月間、胸が張り裂けるようでした。泣く以外、わたしには何もできることはありませんでした」
国内避難民キャンプに身を寄せる母親たちは、ユニセフが支援する職業訓練に子どもを通わせられるとともに、彼女たち自身も利用可能なサービスの紹介を受けることができます。また、18歳未満の子どもたちは、支援が必要な若者たちのための授業を無料で受けることができます。
ハリマさんは調理とビジネスの職業訓練のコースに登録しました。
「無料で授業が受けられるように力を貸してくれる人がいるとは思いませんでした。レストランを開店させるための役に立つと思うので、調理とビジネスの授業を受けています。ほとんどのレストランは男性が経営しています。だから、わたしが女性初のレストラン経営者になりたいです」
ハリマさんはこの夢の実現に向けて一生懸命訓練を受けています。そして、いつか情勢が安定し、子どもたちと再び暮らすことができる日が来ることを望んでいます。
ハリマさんは前向きで、授業に参加できていることに感謝していると言います。「このプログラムに参加した頃、わたしは惨めで、悲しみに打ちひしがれていました。まさか、わたしも訓練を受け、今のような自分になれるなんて思いもしませんでした。カウンセリングを受け、食べ物をもらい、恐れることはないのだと教えてもらいました」(ハリマさん)
ハリマさんはユニセフが支援するプログラムに参加して、強くなれたと語ります。「もし自分も働いて独立することができると分かっていたら、農村部で夫と一緒の生活に耐えることなどしなかったでしょう」
今の社会で変えたいことはないかと尋ねると、ハリマさんは、たくさん変えたいことはあるけれど、まず強制的な結婚がなくなるようにしたいと答えました。
「娘たちには、勉強し、健康に育ち、良い教育を受けてほしいです」とハリマさんが語ります。
3.復帰プログラムで人生が変わった元子ども兵士、ハリドくん(17歳)
ハリドくんは16歳のとき、ソマリア国軍に入隊しました。貧困や飢えから、地元の採用センターを訪れ、訓練を受けるための登録を行いました。その後ジャジーラ訓練キャンプで基本的な訓練を受け、首都郊外にあるアフグーレに送られました。
 |
| © UNICEF Somalia/2014/Abshir |
| ユニセフが支援するセンターで新しい技術を身につける、元子ども兵士。 |
「文字を書くことすらできませんでした。食べ物も十分に得られない生活だったので、軍に入ることを決めました。ジャジーラ訓練キャンプで3カ月の訓練を受けた後、銃をもらい、戦闘に参加するように言われました」
目的も定まらないなか、武装したハリドくんは町をパトロールする若い兵士たちと行動を共にするようになりました。よく、違法の検問所を設置しては、車を停止させていました。しかし何カ月も給料が未払いとなり、ハリドくんはアフグーレの、ユニセフが支援する社会復帰プロジェクトに参加するようになりました。無料の昼ご飯を目当てに参加したハリドくん。たった3日で、授業への参加は飽きてしまったと話します。
しかし、同じプログラムを受けている友達が、ハリドくんを説得しました。
「退屈でしたが、クラスメートに引きとめられました。ぼくの人生が変わりました」
ハリドくんが社会復帰プログラムに再び通い始めた頃、かつて国軍にいたときの仲間に悲劇が襲いました。
「違法で検問を行っていた友達のうち8人が、AMISOMによって殺害されました。もし社会復帰プログラムに参加していなかったら、ぼくもその場にいたと思います。命を救われました」
社会復帰プログラムに参加して4カ月後、ハリドくんは友達とビジネスを始めることを決意しました。ハリドくんは配管作業について、友達は電気工学について学んでいます。ふたりのビジネスは繁盛しているといいます。ハリドくんにとって、学び、ビジネスを始めるという機会が、他の子どもたちのような夢をもたらしたのです。
「以前、ぼくは人に頼っていました。でも、今はぼくが頼られる側です。他の人たちにも、学び、今ぼくが手に入れているようなチャンスを掴んでほしいです」
4.爆弾で片足を失ったファラくん(18歳)
18歳のファラくんが、NGO団体のカウンセリング室でプラスチックの椅子に座っていました。やせ気味で長身のファラくん。少し腰を曲げ、足を前に伸ばして座っています。指を唇のあたりで動かしながら話をし、笑うことも、多くを語ることもありません。穏やかな話し声ですが、一言二言で会話を打ち切り、目を合わせることもめったにありません。
ファラさんは3人の兄弟姉妹のうち、唯一の男の子として、幼い頃から家族を支える立場に置かれていました。16歳の頃、”チャット”と呼ばれる植物を積んだトラックを走って追いかけ、チャットを拾っては集め、モガディシュの青空市場で売っていました。そして2012年のある晩、車が爆発し、すぐそばにいたファラさんは意識を失いました。
「ぼくはチャットを売っていただけです。すぐそばに、爆弾があったのです。手術をするまで、片足を失っていることすら気が付きませんでした」そう話すと、左太ももを触りました。
「傷が治るまで、4カ月かかりました」ファラくんは静かにそう付け足すと、シャツをめくってお腹の火傷や傷を見せました。「母にとって、ぼくが唯一の息子でした。もう、家に帰ってチャットを売ることはできません」
チャットを売っている子どもたちや若者のほとんどが、トラックの後ろを追いかけ、予測不可能な動きをしながらこぼれ落ちるチャットの枝を拾い集め、売ることで生計を立てています。しかし片足を失ったファラくんには、もうその術も残されていません。
「社会復帰センターに来る人たちを目にしていたので、ぼくも参加することにしました。携帯電話についての授業を受けています。座りながら仕事ができますから。ここに来て、友達もできました」そう語るファラくん。仕事に就き、家族を支え、携帯電話ビジネスを志すことができる今、ファラくんは、自分は誰の迷惑にも、負担にもなっていないのだと気付いたと言います。
「このようなプログラムはとても重要です。チャンスがあることを知らずに家にいる人もいますから。仕事に就きたいです。ここに来てから、私の人生は一変しました」
*名前はすべて仮名です。
【関連ページ】
![]()

 保健
保健
 水と衛生
水と衛生 栄養
栄養 教育
教育 子どもの保護
子どもの保護