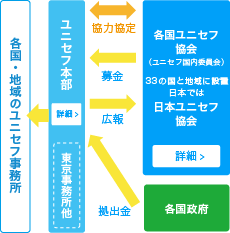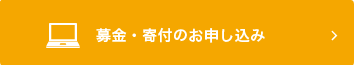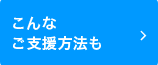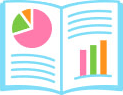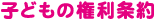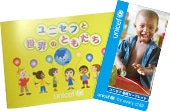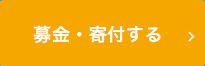2024年5月20日東京発
2024年3月16日、豊田市青少年センターにおいて、セミナー「SDGs(持続可能な開発目標)とCFCI(子どもにやさしいまちづくり)―今こどもの声を聴いて未来を確実なものにするために―」が開催されました。
SDGsの達成期限が近づきつつある一方で、世界は様々な危機に直面しています。正解が見えず先の見通しにくい社会にあって、国単位やおとなだけで持続可能な社会を考えていくことへの限界も指摘されています。
そこで、今回のセミナーでは、未来を確実なものとするために必要なことや、子どもと共に子どもにやさしいまちづくりを進めようとするCFCIが果たす役割について、SDGs未来都市であり2023年から日本型CFCI候補自治体としてCFCIの取り組みを進める豊田市の担当者や、同じ愛知県内に所在し、ローカルレベルのSDGs推進を担当する国連地域開発センター(UNCRD)職員、そして、これまで豊田市子ども会議の委員を務め、今年高校を卒業したばかりの若者と共に考えました。
第一部:問題提起
第一部では、基調講演として2名の登壇者による問題提起が行われました。
問題提起1「国際化の中の子育ち・子育ての地方自治施策としての子どもにやさしいまちづくり」
大妻女子大学 木下 勇 教授(日本ユニセフ協会CFCI委員会委員長)

Ⓒ日本ユニセフ協会
大妻女子大学 木下勇教授
木下教授は冒頭、住民の苦情から公園が廃止された例を挙げ、子どもの権利と高齢者の権利は対立するのか?と投げかけました。
そして、子ども・おとな、乳幼児・学童期などで分断するのではなく、子どもに関わる施設や活動によって人々がつながっていくことの大切さを話しました。さらに、現在の子どもを取り巻く様々な課題を挙げ、SDGsが示す「将来世代のニーズを満たす能力」が損なわれていることを指摘する一方で、その危機を訴えるために行動を起こしている子ども・若者を紹介しました。
そのうえで、1996年に第2回国連人間居住会議(ハビタット2)で提唱され、安心して住み続けられるための都市環境を整え、子どもと共につくる持続可能なまちづくりのために開始された「子どもにやさしいまちづくり事業」について、その歴史や枠組みなどを紹介しました。
主にヨーロッパで推進されてきた様々な子ども参加の取り組みにも触れた後、日本でのCFCIの歴史や枠組み、プロセスなどを説明し、現在CFCIが実践されている5つの自治体の事例を報告しました。
最後に、CFCIは、子どもと子どもが成長する地域のエンパワメントであり、子ども参画のまちづくりを支援する施策であり、自治体での取り組みを国境を越えてつなげていくグローカルな取り組みであるとまとめ、SDGsの達成にCFCIの推進が重要な役割を果たすと結びました。
問題提起2「2030年までの道筋:地方自治体SDGs(持続可能な開発目標)達成評価2023」
国連地域開発センター(UNCRD) 遠藤 和重 所長

Ⓒ日本ユニセフ協会
国連地域開発センターUNCRD 遠藤和重所長
遠藤所長は、2023年がSDGsの目標年2030年に向けた折り返し地点であったことに触れ、「SDGsサミット2023」(2023年7月)に合わせて発表された報告書「持続可能な開発目標報告2023:特別版」(国連本部,2023)を紹介しました。
特に、目標の15%しか軌道に乗っていないだけでなく、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)なども影響し、策定時期から後退しているものさえあることに言及したうえで、2030年までの目標達成には”トランスフォーメーション(変革)”が必要であることを強調しました。
また、地方自治体のSDGsの進捗状況を客観的に評価し、その変化と課題、傾向を明らかにした報告書「2030年までの道筋:地方自治体SDGs達成度評価2023」(UNCRD,2023年9月)を、具体的な分析結果に触れながら紹介しました。全国的に大きく改善しているものもあれば(ゴール17)、全体として改善しているが都道府県ごとの達成度の差が大きいもの(ゴール12・7)、都道府県間の差異は小さいが全体的に達成率が非常に低いもの(ゴール5)など、特徴的なものを報告しました。
さらに、GDP世界4位の日本がSDGsの達成で見ると21位であることを挙げ、2024年に開催される「未来サミット」に向けてGDPに代わる豊かさをどのように測るのかが問われていることなどに触れ、国レベルの評価だけでない、自治体や個人レベルの評価・価値観の重要性も指摘し、「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指すためのローカルSDGsの重要性を強調しました。
第二部:パネルディスカッション
第二部には、国連地域開発センター(UNCRD)の泉川雅子さん、豊田市こども若者政策課の宇佐美由紀課長、豊田市子ども会議の委員や、こども家庭庁の子ども意見聴取のしくみの中心的メンバーである「みんなのパートナーぽんぱー」にも参加し、今年高校を卒業した莇生田和哉さんが登壇し、木下教授の進行でディスカッションが行われました。
UNCRDの泉川さんは、若い世代が、商品選びや就職活動の際、企業のSDGsへの取り組みを判断基準としていることや、その関心が他の世代と比べて圧倒的に高いことを紹介し、遠藤氏の指摘したSDGs目標達成のためのトランスフォーメーションのカギは子ども・若者にあると話しました。
莇生田さんは、豊田市こども・若者総合計画に「子ども・若者視点に立つ」ことが明記されていることを挙げ、どれだけ「視点に立」っても、それはどこまでもおとなの考えであることを指摘。もっと直接子どもの意見を聴くことやそれに対する具体的なフィードバックが必要であることを訴えました。
それを受けて宇佐美課長は、庁内でも子どもの意見を聴くことに温度差があることを実体験を交えて話し、市民の声を聴く既存の枠組みを利用する等、CFCIに取り組む自治体としてもっと工夫をしていきたいと述べました。また、当初の計画に沿って事業を実施するという役所の性格に触れながら、計画の時点で子どもの声を聴いていくことの必要性に言及しました。
最後に莇生田さんは、先が見通しづらい社会の中で子どもたちも頑張っていることを力強く延べ、誰も正解が分からない社会だからこそ、子どもたちの意見を聴くことで未来を確実なものにしていけるのではないかとまとめました。
会場からは、宇佐美課長の前で豊田市への率直な意見を述べた莇生田さんへ、子ども会議への参加動機に関する質問や、質問に対して率直に、誠実に回答した宇佐美課長へ、庁内横断的な取り組みについての質問が寄せられました。

Ⓒ日本ユニセフ協会
左から:国連地域開発センターUNCRD泉川雅子さん、豊田市こども・若者政策課 宇佐美由紀課長、豊田市子ども会議委員 莇生田和哉さん
本セミナーは、公益社団法人こども環境学会の設立20周年記念大会のプレ・セミナーとして、日本ユニセフ協会との共催で開催されました。
こども環境学会は、子どもに関する領域の横断的な学術団体として設立され、よりよい成育環境の実現を目的に多領域の研究者や実践者、子ども会員が、子どもの育ちを軸とした研究、実践、そして社会への提言・発信や啓蒙活動を行っています。20周年記念大会の本大会は、「こどもにやさしいまち・社会を目指して」をテーマに、5月31日~6月2日の3日間、東京で開催されます。


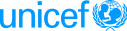
 保健
保健
 水と衛生
水と衛生 栄養
栄養 教育
教育 子どもの保護
子どもの保護