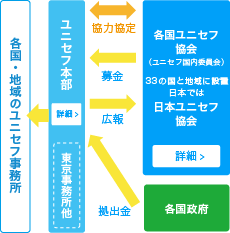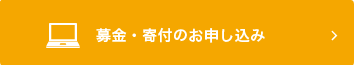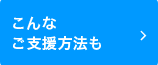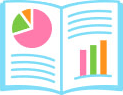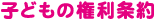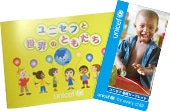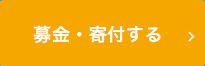2024年6月28日発
サンゴ礁でできた島国

©日本ユニセフ協会/Hironobu Nozawa
タラワ島の両岸(ラグーンサイドとオーシャンサイド)が見渡せる場所(キリバス、2024年5月31日撮影)
太平洋に浮かぶ33の珊瑚礁でできた島からなるキリバス。首都があるタラワ島はひらがなの「く」を逆にしたような形をしています。細長い島で幅が極端に狭く、場所によっては、一方の浜からもう一方の浜がかんたんに見通せます。
人々は満ちては引く海とともに穏やかに生きています。心には「持つものが、持たざるものと分かち合う」という考えが浸透しており、助け合いながら暮らしています。
そんな穏やかで美しい国キリバスですが、気候変動による危機がひた迫っています。ひとつが「海面上昇」。国連諸機関とキリバス政府が発表した評価報告書によると、2080年には最大60.2cmの上昇が予想されています。すでに一部の海岸線が侵食されていますが、島幅が狭いため逃げ場がありません。
ほかにも、暴風雨や干ばつなどの異常気象、高潮など、気候変動の影響によるさまざまな問題が起きています。現状を見つめるため、ユニセフ・アジア親善大使のアグネス・チャンさんが2024年5月末~6月初旬にキリバスを訪れました。
海岸線の侵食で家を失った

©日本ユニセフ協会/Hironobu Nozawa
家と店を流された場所に立つメーレさん家族。背後に壊れた防潮堤がみえる
毎日、干潮と満潮の影響を受けるキリバス。年に数度、地球と月と太陽の位置関係で引き起こされる「キング・タイド」と呼ばれる最大級の満潮時は水位が3メートルを超えます。最高標高が海抜3メートルのタラワ島では、家が浸水したり、流されたりする危険が高まります。
エイタ村に住むメーレさん家族は、2008年ごろ、自宅と経営していた小さな商店を流されてしまいました。「とても大きなキング・タイドがきて、当時まだ幼かった子どもとともに逃げるしかありませんでした」
いま、自宅があった場所は満潮時には海に沈むようになり、一軒の家も建っていません。壊れた防潮堤だけが残されています。
悪化する水資源、ユニセフの支援

©日本ユニセフ協会/Hironobu Nozawa
ユニセフがタラワ島西端のテマキン村に設置した雨水タンク(キリバス、2024年6月1日撮影)
主な水資源は地下水と雨水。地下水は絶対量が不足しているうえ、海面上昇や干ばつの影響で海水が混じる「塩水化」が問題になっています。
雨水にも問題があります。近年では長期化した干ばつが起き、2022年には政府が国家災害宣言を発令したほど。これも気候変動の影響と考えられており、「繰り返されるようなら生活していけなくなる」と住民たちは不安がっています。
「多くのキリバスの人々は自由に水も飲めない暮らしを送っています。でも、みんな一生懸命我慢しているんですね」とアグネス大使。

©日本ユニセフ協会/Hironobu Nozawa
ベケニベウ西保健クリニックで働く看護師と保健員。壁一面に地域住民の健康を把握した統計が貼りだされていた(キリバス、2024年5月31日撮影)
下水道も十分に整備されておらず、海で用を足す屋外排泄も日常的におこなわれています。こうした習慣も水質の悪化に直結する深刻な問題です。実際、同国の5歳未満児の死亡原因に占める下痢の割合は高く、ユニセフは安全な水や衛生設備へのアクセス改善と衛生習慣の啓発のため、水と衛生の支援プログラムを進めています。
ほかにもさまざまな分野の支援活動をユニセフはおこなっています。保健・栄養分野では、看護師と保健員が中心となり、完全地域密着で住民たちの健康に関するデータを収集して栄養管理や予防接種を進めています。また、ユニセフは政府とともにキリバスの気候変動問題を国際社会に訴えたり、キリバスで起こっている気候変動問題について子どもたちに知識と理解を深めてもらったりする活動もおこなっています。
今日はキリバス、明日は私たち

©日本ユニセフ協会/Hironobu Nozawa
ベケニベウ西小学校の子どもたちと対話するアグネス大使。子どもたちは、暴風雨の恐怖や、海面上昇や高潮への不安などを打ち明けた(キリバス、2024年5月31日撮影)
キリバスの温室効果ガスの排出量は、世界銀行のデータがある国・地域のうち、下から3番目。世界全体の0.0002%にすぎません。にもかかわらず、主に先進国の経済活動のしわ寄せから、気候変動問題の最前線に立っている現状があります。訪問の最後、アグネス大使はこう語りました。
「キリバスの人々と触れ合い、少しシャイですが、まわりの人とおたがいに信じあって生きていこう、という愛情あふれる民族性を感じることができました。子どもたちは最高にかわいいです。でもある若者は、気候変動がこの国に与えている影響を考えると、『私は子どもを持たない方がいいかもしれない』といいました。とても悲しいことです。気候変動は世界的な問題で、じつは海抜低い都市は日本も含めてたくさんあります。今日はキリバスの問題、明日は私たちの問題です。キリバスで問題を解決してみませんか。もしキリバスで解決できたら、それは私たちの模範になります」

©日本ユニセフ協会/Hironobu Nozawa
ベケニベウ西小学校で子どもたちに語りかけるアグネス大使(キリバス、2024年5月31日撮影)

©日本ユニセフ協会/Hironobu Nozawa
アグネス大使のレクリエーションに目を輝かせるベケニベウ西小学校の子どもたち(キリバス、2024年5月31日撮影)


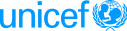
 保健
保健
 水と衛生
水と衛生 栄養
栄養 教育
教育 子どもの保護
子どもの保護