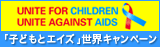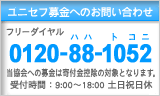|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
| ※地図は参考のために掲載したもので、国境の法的地位について何らかの立場を示すものではありません。 |
レソトは、一人当たり国民総所得(GNI: Gross National Income)が740ドルです。日本のGNIは37,180ドルなので、レソトはとても低いということが分かります。後発開発途上国として、貧困問題を抱えています。人々の失業率は高く、干ばつ被害が頻繁に起こるので、慢性的な脅威にさらされています。
現在は人口の36%(世界子供白書2006統計表7より)もの人が貧困ライン(1日1ドル以下で暮らす状態)未満で生活を送っています。また、レソトのHIV感染率は、スワジランド、ボツワナに続き第3位です。なんと、レソトの約3人に1人がHIVウイルスに感染しているのです。エイズの影響もあって、レソトの平均寿命は2004年に35歳にまで低下しています。
子どもたちは、今、どんな生活を送っているのか。何が子どもたちの生活を脅かしているのか、アグネス大使の視察とその後の報告で詳しくお伝えする予定です。
元ユニセフ・レソト事務所 青少年育成担当官菊川 穣氏(2003年4月) |
| ▲ メニューに戻る |
 レソトは、南アフリカに周囲を囲まれた面積がわずか3万平方キロメートルの小国です。国土の大部分が高地にあり、「アフリカのスイス」、「天空の王国」などと呼ばれています。山が多く、自然はとても美しいです。ポニートレッキングという、馬に乗っていくハイキングが観光客に人気です。
レソトは、南アフリカに周囲を囲まれた面積がわずか3万平方キロメートルの小国です。国土の大部分が高地にあり、「アフリカのスイス」、「天空の王国」などと呼ばれています。山が多く、自然はとても美しいです。ポニートレッキングという、馬に乗っていくハイキングが観光客に人気です。
そんな美しいレソトですが、貧困、干ばつ、そしてHIV/エイズの蔓延によって、レソトの総人口の半分以上の人々が、海外からの食料援助に依存せざるを得ない生活を送っています。
その中でも特に、HIV/エイズの蔓延は世界のなかでも悲惨な状況です。15歳から49歳の人々の有病率は約29%です。この病気の流行により、1990年には平均寿命が58歳だったのが、2004年には35歳になってしまいました。これは大変なことです。
緊急食糧援助は、各国が行っていますが、レソトが2015年までに飢餓と極度の貧困を根絶させるという目標(ミレニアム開発目標1)は達成できないのではないかと言われています。
■ レソトの子どもたちが直面している問題

- 孤児や困難な状況におかれている子どもたち(世帯主にならざるを得なくなった子どもたちもいます)は、現在の食料危機で最も危険にさらされています。孤児の数は約18万人まで増えました。
- 妊婦死亡率は1990年以降上昇しています。
- 青年の多くは、HIVの危険性について知っていますが、それでも、多数の相手との性交渉をもったり、コンドームを使用していなかったりします。また、レイプや性行為の強制がエイズの流行に拍車をかけています。
- 抗レトロウイルス薬を必要としている人々は約5万6千人です。そのうちの人々のたった2000人が薬をもらえている状況です。
- 女子の就学率が下がりつつあります。それは、両親が死んでしまったので家族の面倒をみざるを得なくなっているからです。
- レソトの憲法では、女性は男性の親類の後見を受けるものと規定されてます。
■ 子どもたちのための活動とその結果

- レソトの政府は、ユニセフが主に導しているPoverty Reduction Strategy (貧困削減戦略)を認めました。
- 政府は国内初となる抗レトロウイルス治療センターを作りました。
- 妊婦の25%は現在、HIVのカウンセリングと検査が行うことができるクリニックに通っています。そのうち3分の1の女性は、HIVウイルスを生まれてくる子どもに感染させる(母子感染)のを防ぐ教育を受けています。
- ユニセフと協力団体は、HIV/エイズとライフスキル(日常生活における多種多様な問題や要求に、建設的かつ効果的に対応する際に必要とされる能力)を教えることのできる先生とその先生を教育する立場の人たちの訓練を行いました。現在、500人の先生と、先生を教育する100人の先生が訓練を受けました。
- Girls Education Movement (女子教育運動)を行い、7000人の若い男女がHIV/エイズの感染予防の知識を勉強し、同じ若者に情報を伝えられるようになりました。また全ての子どもたちが平等に教育受けられるようなキャンペーンを行うことができるようにしました。
- ユニセフと協力団体は虫下しやビタミンA補給剤を9000人の子どもたちに配りました。
- レソトの自治省は、警察庁のなかに、Child and Gender Protection Unit(子どもとジェンダー保護課)を設置しました。これは、女性と子どもの権利を保護するためにとても重要な役割を果たすものです。 これから警察官になろうとする人たちはみな、コミュニケーション、カウンセリングの技術の研修をうけるとともに、人権を守ることの必要性を学ぶ教育を受けています。
| ▲ メニューに戻る |
- 以下の統計は、UNICEF ホームページ INFO BY COUNTRY "Lesotho" Statistics に掲載されている統計の数字を転載しました。
- 今回は5歳未満児死亡率、18歳未満の人口、一人あたりのGNIなどの基本統計に加え、 HIV/エイズに関する統計を中心にピックアップしました。
- 2003年末の統計では、成人のエイズ有病率の高い上位4カ国(スワジランド、ボツワナ、レソト、ザンビア)で、平均寿命が30歳代という危機的状況に陥っていることが明らかになりました。エイズによる孤児の問題も深刻化しています。
- 詳しい統計は最新版の世界子供白書、もしくはUNICEFホームページ INFO BY COUTRYをご覧ください。
|
| ▲ メニューに戻る |
■ タカツォ君の場合
 タカツォ君はお母さんと一緒に、レソトの首都マセルから10キロほど離れたリタバネに住んでいました。お母さんは織物工場に勤めていて、二人とも幸せに暮らしていました。
タカツォ君はお母さんと一緒に、レソトの首都マセルから10キロほど離れたリタバネに住んでいました。お母さんは織物工場に勤めていて、二人とも幸せに暮らしていました。
しかし、現在レソトのマセル子ども村に住むタカツォ君と妹の赤ちゃんレラトちゃんは孤児です。お母さんは妹を生んだ後にエイズで亡くなってしまいました。
2人ともHIV陽性です。彼らのお母さんは正式に結婚していなかったので、お父さんは生まれた時からいませんでした。親戚は、一人の叔父さんを除いて全員、彼らの面倒を見たくないと言いました。しかし、その一人の叔父さんも、今は刑務所にいます。
お母さんが病気で倒れてしまい病院に運ばれたとき、タカツォ君はたった一人で取り残されました。どうしたらいいか分からないでいると、近所の人が心配して通報してくれたので、レソトにあるマセル子ども村に連れてこられました。
村のソーシャルワーカーは、タカツォ君にお母さんは病気で、妊娠もしているから、治るまでしばらく待っていようねと言いました。しかし、お母さんは赤ちゃんを生んだ後、そのまま回復することなく死んでしまいました。
タカツォ君はしばらく赤ちゃんと会えることもなく一人で村の子どもたちやソーシャルワーカたちと暮らしていました。村では一日三度の食事も与えられ、また勉強することもでき、服もきちんと着て生活することができました。しかし、タカツォ君の心の傷はとても深く、心が不安定な状態が続いていました。
しかし、最近、ソーシャルワーカーの努力によって、18カ月になったレラトちゃんが村に連れてこられ、タカツォ君と一緒に暮せるようになりました。彼は何カ月かぶりに笑顔を見せ、妹とずっと遊んでいました。
ユニセフはマセル子ども村で、エイズによる孤児の心のケアや生活面でのサポートをしています。そして、子ども達を親戚で引き取ってくれるよう手配したり、また養子として引き取ってくれる家族を探しています。
タカツォ君とレラトちゃんは現在安全な暮らしをしています。しかし、レソトの中にはエイズで親を失っても誰からも助けてもらえない子ども達が数多くいます。そのような子ども達はストリートチルドレンになったり、危険な児童労働の被害にあったりするケースもあります。そのようなことが起こらないようにユニセフ、レソト政府、協力団体で一致団結して、エイズで親を失った子どもたちが安全で温かい環境で生活できるように努力しています。
■ カモヘロ君とマテ君兄弟の場合
 カモヘロ君とマテ君の兄弟は、3年前まで学校に行って、普通の暮らしをしていました。レソトでは、学校には、日本よりも大分大きくなってから行きます。それは、学校までの道が遠く危険だからです。彼らは19歳と18歳の時に学校に行けなくなりました。二人とも将来の夢があったのにです。
カモヘロ君とマテ君の兄弟は、3年前まで学校に行って、普通の暮らしをしていました。レソトでは、学校には、日本よりも大分大きくなってから行きます。それは、学校までの道が遠く危険だからです。彼らは19歳と18歳の時に学校に行けなくなりました。二人とも将来の夢があったのにです。
それは、両親が亡くなってしまったからです。村の人々は持病で亡くなったと言っていますが、おそらくエイズでしょう。レソトの人々はエイズで人が死んでもそれを隠そうとします。
きょうだいには、他に3人の幼い妹と1人の弟がいます。カモヘロ君とマテ君は学校を辞めて、兄弟を養っていかなければならなくなりました。現在、みんなで泥でできた家に住んでいます。しかし、更なる不幸が彼らを襲いました。それは、彼らの家の牛が盗まれたことです。マテ君は誰が盗んだかは分かっているけど、村の誰も証言してくれないと言っています。
幼いきょうだいはみな、学校に通っています。それは、レソトで5年前に導入された無償初等教育政策 (日本でいう義務教育を無料で受けられる権利にあたります)という政策があるからです。
ユニセフはこの政策をすすめるお手伝いをしました。さらに、HIV/エイズに関する教育ができる先生も養成しています。その先生たちが子ども達の心のケアが出来るようになるからです。
現在カモヘロ君は村で農業や動物飼いの仕事をしています。マテ君は、小さな雑貨屋で働いています。しかしマテ君の収入は1カ月で50ドルにもならず、6人の家族を養うので精一杯で、自分で使うお金はありません。
カモヘロ君の家族は3カ月間に一度、食料の配給を受けています。しかし、彼はいつこの援助がなくなってしまうか分からないから、自分で技術を身に付けて、もっと良い仕事につきたいと願っています。彼は夏の収穫のために村の畑に種をまいています。種を自分の畑に植えるだけもらえたらいいなと思っています。
ユニセフは、カモヘロ君の家族に農作業用の道具や種をあげました。これは、子どもが家族を養っていかなければいけない家族に対する支援プログラムの一つです。このプログラムのおかげで、前回の収穫期にはいつでも新鮮な野菜が自分の庭にありました。また、彼らは、がんばって作業することによって自分たちの生活がよくなるということも学びました。
農業用の道具は、ただ畑を耕すという利点以外にもとても素晴らしい効果がありました。子どもは道具で遊ぶのが好きです。そして、庭で道具を使って耕すことが楽しくなりました。このように、精神的な面からもこのプログラムはとても良い影響を子ども達にもたらしています。
現在、カモヘロ君たちのように両親が死んでしまって、子どもが世帯主になっている家族が2000家族にものぼります。カモヘロ君たちは両親が亡くなった悲しい気持ちなどを抑えて、幼い兄弟の面倒をみなければいけません。
ユニセフは、子ども達には明るい未来があって、健康で、教育も受けられるよ、ということを分かってもらうためにこれからも様々なプログラムを実施していきます。
![]()
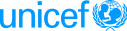
 保健
保健
 水と衛生
水と衛生 栄養
栄養 教育
教育 子どもの保護
子どもの保護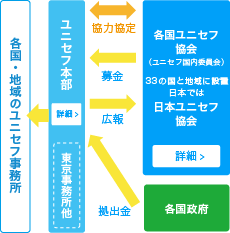


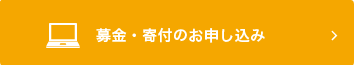

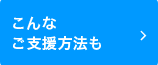



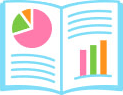
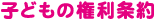


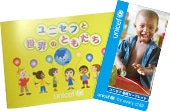






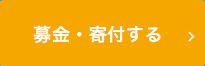
 アグネス・チャン日本ユニセフ協会大使は、2006年4月、レソトを訪れます。
アグネス・チャン日本ユニセフ協会大使は、2006年4月、レソトを訪れます。