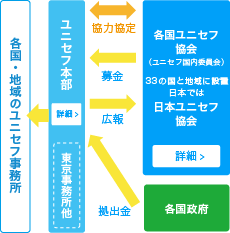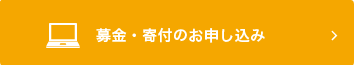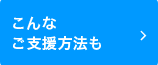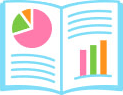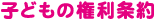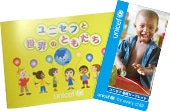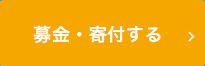2025年1月31日東京発
日本ユニセフ協会は、環境省が昨年12月27日から本年1月27日にかけて実施した「地球温暖化対策計画」の改訂に向けたパブリック・コメント(意見公募)に対し、ユニセフの知見等に基づいた意見を提出しました。
日本国内で地球温暖化対策を推進するための枠組みを定めた「地球温暖化対策の推進に関する法律」(1998年10月9日公布)では、政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な促進を図るため、「地球温暖化対策計画」を定めるとしています。このたびの意見公募は、2021年10月に閣議決定された現行の地球温暖化対策計画の見直しにあたり、新たな計画案に対する意見を募集したものです。
日本ユニセフ協会は、約190の国と地域で活動するユニセフの知見や、国連子どもの権利委員会が2023年に発表し、その編纂にあたり当協会も日本の子どもたちの意見集約に協力した「気候変動に焦点をあてた子どもの権利と環境に関する一般的意見26*」などを元に、下記の通り意見を提出しました。
*「一般的意見」は、国連子どもの権利委員会が、子どもの権利条約に定められた権利が特定のテーマや分野において何を意味するのかについて、法的指針を提供する文書です。一般的意見26は、気候危機や生物多様性の喪失、環境汚染を取り上げ、子どもたちの命や生活を守るために各国が何をしなければならないかを示しています。
地球温暖化対策計画案に対する意見公募について
本案をまとめるにあたり若者世代の声を聴取されていること、また本案が、地球温暖化対策を推進するにあたり同世代の声を聴くとし、若者自身やこれから生まれてくる将来世代の未来に対する不安にも触れていること、さらに、子どもをはじめとする気候変動の影響に脆弱な人々への、地域・性別・世代を超えた気候正義に基づく人権的配慮の視点の重要性に触れていることを高く評価します。その上で、従前よりユニセフ(国連児童基金)がCOPなどの場において国際社会と共有している現状認識を踏まえ、下記頁の中で、以下のとおり気候変動が既に多くの子ども・若者へ与えている影響に言及することを要望します。
1頁(22): 「さらに、気候変動は、既に自然と人々に対し広範な悪影響をもたらしており、突発的かつ不可逆的な変化が起こる可能性は、地球温暖化の水準が高くなるにつれて増加するとされている。」を以下に修正。 「さらに、気候変動は、既に自然と人々に対し広範な悪影響をもたらしており、世界の18歳未満の子どもの約2人に1人は、異常高温や干ばつ、危機的な水不足、大洪水、感染症の拡大など気候変動がもたらした様々な危機に晒されている。こうした状況が今後拡大する可能性は、地球温暖化の水準が高くなるにつれて増加するとされている。」
25頁(17): 「また、自然災害の多発・激甚化やエネルギー・食料問題の深刻化等により、地球温暖化対策がより一層喫緊の課題になっていること、東日本大震災及び原子力発電所事故並びに新型コロナウィルス感染症の世界的なまん延等を契機とし、近年の国民のライフスタイルや意識に変化が生じていること等を踏まえる。」を以下に修正。 「また、自然災害の多発・激甚化やエネルギー・食料問題の深刻化等により、こどもや若者、これから生まれてくる将来世代に不公平な、長期にわたる影響を及ぼすことから、地球温暖化対策がより一層喫緊の課題になっていること、東日本大震災及び原子力発電所事故並びに新型コロナウィルス感染症の世界的なまん延等を契機とし、近年の国民のライフスタイルや意識に変化が生じていること等を踏まえる。」
理由: ユニセフは上記の現状認識に基づき、以前より子どもの視点に立った気候変動対策を訴えています。昨年、UNFCCC史上初めて「子ども」をテーマに開催された第60回補助機関会合(SB60)でも、「UNFCCCのワークストリームや構成機関の作業、NDCs3.0を含む国レベルの政策において、子ども特有の脆弱性への配慮と対策を効果的に統合する」ことを主旨とする提言がまとめられました。また、国連子どもの権利委員会は、弊協会の呼びかけで集まった日本の子ども約1500名を含む世界の子ども・若者から意見聴取のうえ、まとめた「気候変動に焦点をあてた子どもの権利と環境に関する一般的意見26」(2023年)において、環境や気候変動に関係することを決める際、締約国は、それらによって子どもがどのような影響を受けるのか、また現在と将来の子どものウェルビーイングと成長をどのように支えるかを考えなければならない」としています。
子どもの権利に基づく「こどもまんなか社会」の実現に向けて様々な取り組みを進められている日本政府が、地球温暖化対策においても子ども・若者が権利の主体であるという視点に立ち、子どもの権利を尊重し、守り、実現する姿勢を示していただけるよう要望します。


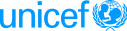
 保健
保健
 水と衛生
水と衛生 栄養
栄養 教育
教育 子どもの保護
子どもの保護