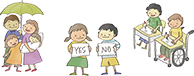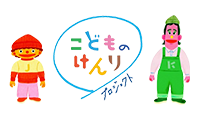2021年2月20日ソマリ州(エチオピア)発

© UNICEF Ethiopia/2024/Sahilu
ムクレムさん。学校を中退した女の子たちを対象にした支援プログラムで、参加者のサポート役を務める(エチオピア、2024年撮影)
女性器切除(FGM)とは、アフリカや中東、アジアの一部の国々で行われている、女性の性器の一部を切除してしまう因習です。女の子と女性の身体とこころに、生涯消えることのない深い傷跡を残します。エチオピア東部のソマリ州でも、地域の文化的・社会的規範に深く根ざす形で、これまでFGMが実施されてきました。2016年のエチオピア国内の人口保健調査によると、同州でのFGMの実施率は極めて高く、15~49歳で99%、15~19歳で95%に上ります。また同様に、18歳未満で結婚する児童婚の割合も49.4%に上っています。
そうしたなか、ユニセフはソマリ州において、FGMや児童婚のような有害な因習を根絶するため、さまざまな層の人々を対象にした啓発活動に力を入れて取り組んでいます。思春期の女の子たちだけでなく、地域の男性や男の子たちに対しても働きかけを行い、地域社会全体に変化を促すことを目指しています。
ここでは、啓発活動に参加して、FGMと児童婚の根絶に向けて行動を起こした5人の声を紹介します。
ムクレムさん:「実際の変化に、やる気と勇気をもらっている」
ソマリ州のケブリバイヤ地域で暮らすムクレムさん(20歳)は、学校を中退した10~19歳の女の子たちを対象にした支援プログラムで、参加者のサポート役を務めています。同プログラムの一環で、週1回の頻度で全19回開催されるワークショップでは、1グループ25名の女の子たちが、コミュニケーションスキルや自己理解を向上させる内容のほか、FGMや児童婚の問題について学びます。ムクレムさんたちの取り組みを支持する人もいれば、無駄だと否定する人もいますが、ムクレムさん自身は「大多数の人は私たちの味方で、反対する人はごくわずかです」と、状況を前向きにとらえています。「私たちのコミュニティが良い方向に向かい、実際に変化が見られていることに、やる気と勇気をもらっています」と話します。
ラミカさん:つながる想い「友人たちを有害な因習から守りたい」

© UNICEF Ethiopia/2024/Sahilu
FGMや児童婚の問題について学ぶプログラムに参加したラミカさん(エチオピア、2024年撮影)
ラミカさん(15歳)も、ユニセフが支援するプログラムに参加した一人です。母親がしばらくの間家を空けることになって学校を中退した際、周りの友人たちに声を掛けてもらったことがきっかけでした。友人たちは、ラミカさんがこの年齢で結婚してしまうのではないかと心配して、ラミカさんにプログラムへの参加を促したといいます。プログラムに参加した後、ラミカさんは復学を決意しました。「もし他の子が学校を中退することがあれば、友人が私にしてくれたように、このプログラムに参加するよう誘うわ」とラミカさんは話します。ワークショップを通して、感染症や不妊をはじめとする、FGMが女性の健康に及ぼす影響を学んだことで、ラミカさんは将来医師になりたいと考えるようになりました。
ブセリさん・アンワルさん兄弟:「同世代の男の子たちにも意識の変化」

© UNICEF Ethiopia/2024/Sahilu
ブセリさんとアンワルさんの兄弟。男の子を対象にしたFGMや児童婚の問題について学ぶプログラムに参加している(エチオピア、2024年撮影)
FGMや児童婚の問題について学ぶプログラムは、思春期の女の子だけでなく、男の子に対しても開催しています。ブセリさん(18歳)とアンワルさん(14歳)兄弟もプログラムに参加しています。
ワークショップでファシリテーターを務める兄のブセリさんは、「私と同世代の男性たちは、FGMを支持していません。女性の健康に悪影響を及ぼすからです」と話します。弟のアンワルさんは、FGMと児童婚という因習が有害で間違っていることを、友人たちに積極的に伝えています。また、こうした啓発活動を通じて、コミュニティにおいてFGMと児童婚の件数が減少していることを実感していると、兄弟は口を揃えて言います。
ハムディさん:「娘たちにFGMを受けさせるつもりはない」

© UNICEF Ethiopia/2024/Sahilu
7人の子どもを育てるハムディさん。娘たちにはFGMを受けさせないと話す(エチオピア、2024年撮影)
ユニセフは、思春期の子どもたちを対象にしたワークショップ開催の他にも、家々を訪問してFGMや児童婚の問題を家族に伝える啓発活動も行っています。
娘2人を含む7人の子どもを育てるハムディさん(27歳)も、訪問型の啓発活動を通して児童婚とFGMの問題を学んだことで、これらは有害な因習であるという思いを強めました。「児童婚は、出産や月経における困難が増すなど、女の子たちに多くの悪影響をもたらします。そして個人的には、娘たちにFGMを受けさせるつもりはありません」と断言します。ハムディさんは、これらの問題に対する地域社会の理解は、以前と比べ、大きく進んだと感じています。地域の人々の間で、子どもたちが学校に通い、健康的な生活を送れることを願う気持ちが強くなっている――。そう感じています。
FGM根絶に向け、連携強化を
ユニセフは2008年より、国連人口基金(UNFPA)と共同で、FGM根絶のための共同プログラムを実施しています。これまで同プログラムにより、約700万人の女の子と女性が、FGMの予防・保護サービスを受けられるようになりました。また、啓発・アドボカシー活動を通じて、4,800万人がこの因習を放棄すると宣言し、2億2,000万人がこの問題に関する発信をマスメディアから受け取りました。
今なお、2億3,000万人以上の女の子と女性がFGMによる有害な影響を受けるなか、2030年までにFGMを根絶するというSDGs(持続可能な開発目標)の目標に向けて、ユニセフは各リーダーや市民組織のほか、保健、教育、社会的保護の各分野間の連携の強化を求めています。