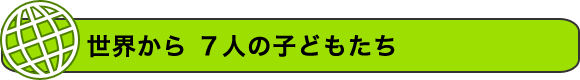
 |
| |
 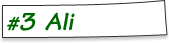
アリ 16歳 <ヨルダン>
ヨルダンで暮らすアリは、一日中小さなレストランで働き、家族の生活を支えています。料理をするかたわらで、友達が遊んでいるのを見ながら、あの輪に入りたいと心から願っています。
|
|
 |
アリは、スフ・キャンプで暮らしています。ここは、1948年以降、ヨルダンに逃れてきた180万人のパレスチナ難民のためにつくられた6つのキャンプのうちのひとつです。
アリは、毎日毎日、レストランで、ヒヨコ豆のコロッケを揚げ、サンドイッチを作り、店の掃除をして、働いています。学校に通っている間は1日6時間、夏休みには1日12時間、働きます。アリが働いている間、友達が通りでサッカーをして笑いあっているのが見えます。アリはずっと、その輪に加わりたい、一緒に遊びたいと思い続けてきました。でも、アリのお父さんは背中と目がひどく悪く、働けません。アリが家族の生活を支えるために働かなければならないことはよく分かっているのです。
アリにとって、毎日長時間働くということは、単に遊ぶ時間やティーンエイジャーとしての生活を犠牲にする、というだけではありません。文字通り、健康を失う危険とも隣り合わせです。2年前、彼は、ヒヨコ豆をつぶしている最中にうっかりうたた寝をして、危うく手を失うところでした。幸運にも、すぐに病院に駆け込み、事なきを得ました。
スフの17000人の住民の生活は殺伐としたものです。仕事は少なく、多くの難民が近隣の農場でオリーブ摘みなどの日雇い仕事をしています。キャンプで暮らす3400人の10代の子どもたちは、お互いに会ったり、友達付き合いをする場もなく、将来にも期待を持てずにいます。
そんな中、スフ・キャンプで10代の子どもたちに映画づくりを教えようというプロジェクトがもちあがった時、子どもたちは大興奮でした。プロジェクトは、子どもたちに自分自身を表現する場を与え、若者達の社会への参加を促そうという目的で企画されました。子どもたちは、撮影の仕方や、編集方法、脚本の書き方なども学びました。
「これは子どもたちの目を大きく開かせたのです」とプロジェクトを指揮したバシャール氏。「子どもたちは学校で暗記中心の学習に慣らされてしまっていて、最初、自分自身を表現したり、異性に話しかけたりすることがとても難しかったようです。でも、子どもたちはすぐにきっかけをつかみ、自分たちに関わる問題を自由に話しはじめたのです」
参加した子どもたちは、どのようなテーマを取り上げるべきか、自由に意見を出し合いました。最後に、家族を支えるために働かなければならない子どもたちの願いをテーマにしようと結論が出ました。そして、アリが主役に選ばれたのです。
いったんテーマが決まると、子どもたちは脚本を書き始めました。そして、キャンプ内の生活を撮影し、編集しました。
「この映画は個人的な“叫び”なんだ。ぼくらはこれを広めたいと、キャンプの外で暮らす人々にもぼくらの生活がどんなだか知ってもらいたいと思ったんだ」とアリ。「つらいさ。だけど、もっとつらいのは、ぼくらの年代の若い子どもたちが、みんなと違うことをしているからって見過ごされたり、変に特別視されたりすることなんだ」
アリは、ヨルダンで働く4万人の子ども(7〜18歳)のうちのひとりです。世界には、推定で2億4600万人の子どもが児童労働に従事しています。そして、その70%近くは、有害で過酷な状況下での労働を強いられています。例えば、炭鉱で、化学薬品や農薬を扱う場所で、危険な機械を扱う場所で。彼らはどこにでもいます。なのに、ほとんどの場合、彼らの存在は“目に見えない”のです。お手伝いとして家の中に押し込められていたり、工場の壁の向こうに隠されていたり…。彼らの叫びを、どうにかして聞こえるようにしなければなりません。
アリたちの映像はこちらから(英語)

|トップページへ|先頭に戻る|

