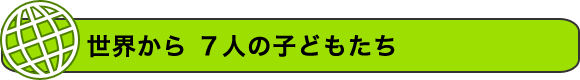
 |
| |
 
ケベッツェ 12歳 <ボツワナ>
ケベッツェはボツワナで暮らす孤児です。お母さんが(恐らくエイズによって)亡くなってから、祖母と一緒に暮らしています。ケベッツェは、1日の大半を街ですることもなくぶらぶらとうろついています。というのも家にいると祖母から虐待にも似たひどい扱いを受けるので、それから逃げるために仕方なく街へ出るのです。ですが、最近は、ケアセンターに通いはじめ、読み書きを学ぶようになりました。
|
|
 |
ボツワナ、カニェの街の喧騒のなかを歩くケベッツェ。その姿からは、せいいっぱい強い男に見せかけようとしているのが伝わってきます。
ものごころがついた頃からずっと孤児だったケベッツェはどうして母親が亡くなったのか知りません。
母親が亡くなると、ケベッツェは16歳になる兄と一緒に祖母にいやいや引き取られました。「おばあちゃんは、ぼくやお兄ちゃんを見るといらいらすると言うんだ。そして、ぼくらをぶつのさ。時にはぼくらを放り出したり、いつも、お前達の母親が死んだからって私にはお前たちの面倒を見る義理はないんだからね、と言うんだよ」
祖母の虐待から逃れるために、ケベッツェはほとんどを街なかで過ごすようにりました。でも、ときどきは学校に通っています。彼は、街は子どもたちのいる場所ではない、とよく分かっています。そんな彼の心のうちがあらわれるのは、ボナ・レセディ(希望を見つけるという意味)という孤児たちのためのデイケアセンターにいるときです。ボナ・レセディで、ケベッツェはノノ・モレファ先生の肩にもたれかかって、すっかり小さな子どもに戻り、人の関心を引き、抱きしめてもらいたいとねだるのです。ノノ先生はそんなケベッツェを受けとめ、ねだられるままに手を差し伸べています。
安心できる場所を見つけたケベッツェは、より良い生活を見つけようと希望を持ちはじめました。そして、「街でだって生きられるさ」といきがることをやめました。
「HIV/エイズがすごい勢いで広がりはじめてから、ケベッツェのような多くの子どもたちの基本的なニーズが満たされなくなりました。子どもたちには教育が必要です。愛情も食べものも、それから時にはシェルターも。私達は、彼らに衣服を与えたり、学校の宿題を手伝ったりします。彼らは眠るためだけに家に帰るのです」とノノ先生は話します。
カニェの街だけで、約2000人の孤児がいます。センターに通っているのはわずか200人にすぎません。実際に何人の子どもが支援を必要としているのか、より詳しく調べることも重要です。
ボツワナで孤児が増え続けているのは、明らかにHIV/エイズが直接の原因です。HIV/エイズは世界中のどこよりもサハラ以南のアフリカ地域を直撃しています。この惨禍により、この地域では1200万人の子どもたちが、親と子ども時代をうばわれています。
世界で2番目にHIV/エイズの感染率が高いボツワナでは、子どもたちの実に15%が孤児となっています。そして、感染の勢いは現在も続いており、過去に例を見ないほどの数の子どもたちが、親や親族による保護の輪から取り残されてゆくことになります。
今の状況下では、ケベッツェのような子どもたちにとって、ボナ・レセディのようなセンターだけが、たったひとつの将来への希望なのです。
ケベッツェの映像はこちらから(英語)

|トップページへ|先頭に戻る|

