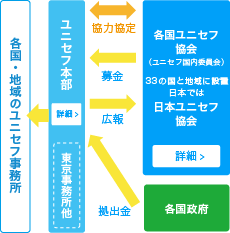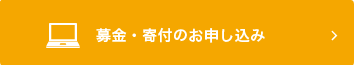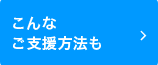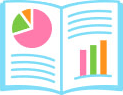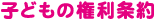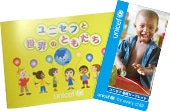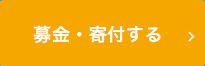|
HOME > ニュースバックナンバー2014年 > ストーリーを読む
|
|
|
緊急支援情報
|
||||||||||||||||
|
東日本大震災復興支援 第247報
|
|||||||||||||||
 |
| © 日本ユニセフ協会 |
| 里親子支援セミナーの様子(気仙沼市) |
「里親月間」と「児童虐待防止推進月間」。毎年10月と11月は、様々な理由でお母さんやお父さんと一緒に暮らすことができなかったり、適切な関係を持てなかったりする子どもたちのことを社会全体で改めて考えることが訴えられる時期です。
日本ユニセフ協会は、親を失った子どもたちの保護の観点から、全国児童家庭支援センター協議会と恊働し、宮城県気仙沼市と岩手県気仙地区で「里親子支援事業」に取り組んでいます。
11月17日、気仙沼市の児童養護施設「旭が丘学園」に併設される児童家庭支援センターの主催、気仙沼市社会福祉協議会、気仙沼市民生委員児童委員協議会の共催、日本ユニセフ協会の支援で、「社会で支える子育て、地域に根ざした子ども・子育ての実現を目指して」と題するセミナーが行われました。
今回のセミナーには、地元の民生委員や児童委員、里親、ボランティアクラブの他、他県の児童家庭支援センターの職員の方々など、100名ほどの方々が参加。関西大学教授の山縣文治さんから、「地域の福祉活動と里親子支援」と題して講演。地域での子育て支援のすすめ方を中心に、お話をいただきました。
 |
| © 日本ユニセフ協会 |
| 先入観でものを考えていないか、「カモシカの角」をイメージしてみるというワーク(山縣さんによる講演の中で) |
「里親家庭で育つ里子は、周囲との違いからいじめられたり、疎外感を覚えたりする。里親も一般の子育ても親子関係を育むのは地域です。誰かにかかる負担を地域全体で分かち合うための取り組みが、欠かせません。震災をきっかけとして、被災地に新しい縁が生まれています。地域全体が見守っていた昔との違いや被災地の現状もありますが、子どもが家庭・地域・学校の輪の中を歩むことには変わりありません。血縁だけではなく、地震などさまざまの災害があるので、地域全体で子どもを見守っていく仕組みづくりが大切です」(山縣さん)
「旭が丘学園」児童家庭支援センターの菅原昭所長は、「もともと気仙沼は里親登録者が多い地域ですが、最近は里親希望者が減ってしまっているので今後もこうした啓発活動を続け、地域の理解を深め里親子支援の充実を図っていきたい」と語ります。参加されたある民生委員の方からは、「里親へ地域としてどのように関わっていけばよいのか考えるきっかけとなりました」といった感想も寄せられました。
全国児童家庭支援センター協議会の副会長で、日本ユニセフ協会との「里親子支援」連携事業を担当する坂口明夫さんは、「震災後は、震災孤児の多くは里親家庭で養育されています。まずは、里親制度の理解や里親子の課題をしっかり地域社会が理解し、サポートできるようにすること。支援者のネットワークをしっかり構築していくお手伝いを続けていきたいと思います」と、熱意を込めて語られました。
![]()
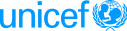
 保健
保健
 水と衛生
水と衛生 栄養
栄養 教育
教育 子どもの保護
子どもの保護