東日本大震災復興支援 第212報
里親子家庭をサポートするために
岩手、宮城、福島の実践を国際会議で報告
【2013年9月15日 大阪発】
 |
| © 日本ユニセフ協会 |
|
東日本大震災の発生から2年半。被災地では、親を失った子どもたちを支える家庭や社会、行政のあり方など、さまざまな問題が浮き彫りになっています。また、復興への明確な道筋がなかなか描かれない状況の中で、子どもへの虐待や心の問題も、一部で深刻化しはじめています。
9月13日から4日間の日程で開催されたIFCO (International Foster Care Organization:国際フォスターケア機構)大阪世界大会のなかで、日本ユニセフ協会は、「震災と子ども」をテーマにした特別シンポジウムを助成し、開催しました。IFCO(イフコ)は、子ども中心の社会的養護と家庭養護の促進と援助を目的とした、国際的ネットワーク機構です。フォスターケアをはじめとした「社会的養護」への関心は世界的に高く、今回アジア初の開催となった今大会には、子どもからおとなまで、25カ国から1000名以上が参加しました。
シンポジウムは、第一部の森田明美氏(東日本大震災子ども支援ネットワーク事務局長)による基調講演と、第二部のパネル討論の二部構成で行われました。
“若者たちを孤立させない”が合言葉
 |
| © 日本ユニセフ協会 |
|
東日本大震災によって両親を亡くした孤児の数は241人、どちらかの親を亡くした遺児の数は1,483人(2013年3月現在、厚生労働省発表)。ほとんどの孤児・遺児は、祖父母やおじ•おばなどの親族に養育されており、今後、養育者の高齢化や健康問題などの課題が懸念されています。また、津波被害により沿岸部の広範囲が居住できない状態になり、内陸部に多くの人口が流入しました。それにより、学校の校庭や公園が仮設住宅で埋まり、遊び場を失った子どもたちはストレスを十分に発散できない環境で生活しています。
「子どもたちを孤立させないために大人との接点をつくることが重要」と強調するのは、基調講演に立った、東日本大震災子ども支援ネットワーク事務局長の森田明美氏。森田氏は、ご自身が代表を勤めるNPO法人が岩手県山田町で行っている支援活動「ゾンタハウス」(中高生やお母さんたちの活動スペース)での経験から、中でも、中高校生が、社会的に脆弱な存在であるにもかかわらず、ほとんど支援を受けられていないと訴えます。また、子どもに対する多様な支援が展開される中で、支援の質の検証が不足しているとも指摘。「寄付やボランティアの提供は、支援を受ける現地の方々が拒否し難いものだからこそ、支援をする側の自己評価がとても大切なのです」と語る森田氏は、「被災者はもちろん、支援者も疲労しています」と、行政と市民社会との協働の必要性も強調されていました。
「震災があって多くの大人を見てきました。僕たち子どもは大人の背中をみて育ちます。なので、これからも頑張る人が増えればよいと思います。」 公演の締めくくりにあたり、森田氏は、ゾンタハウスに遊びに来た山田町の子どものメッセージを紹介しました。
「子どもたちは、涙が出るほど、本当に大人たちのことを想っています。だから(支援にあたっているみなさんには)頑張ってほしい」(森田氏)
社会的養護の課題
 |
| © 日本ユニセフ協会 |
|
第2部のパネルディスカッションでは、日本ユニセフ協会が、震災発生直後から様々な形でサポートしまた協働してきた岩手、宮城、福島各県の自治体や団体、専門家の方々から、これまでの支援の成果と、直面し、見えてきたさまざまな課題が報告されました。
岩手県からは、県保健福祉部児童家庭課の米澤克徳氏と大船渡市の児童家庭支援センター大洋(児童養護施設大洋学園)の刈谷忠氏が参加。沿岸児童相談所による孤児・遺児など要支援児童の把握や、県による遺児家庭支援専門員の配置、里親支援機関の設置などの取り組みを報告。被災児童の心のケアに対応するため、県は、盛岡市内に『いわて子どもケアセンター』を設置し、大洋学園が同センターと連携し『気仙•子どものこころのケアセンター』として機能していることなど、中長期的な社会的擁護の形づくりを念頭にした取り組みが行われていると説明しました。
「岩手県では里親同士の交流や一人親家庭支援を行っているが、今年に入り、問題のなかった子どもが突然不登校になるなど、潜在していた問題が顕在化してきているようだ」「震災前から必要とされていたことであるが、支援者同士の連携が欠かせない」と刈谷氏が報告。米澤氏も、「行政もなんとかしなければとは思っているが、心のケアは手さぐり。もっと早い段階から助けを求めてくればと思うケースが多い」と語ります。
宮城県から参加した県里親会(日本ファミリーホーム協議会)のト蔵康行氏は、同会が、県の親族里親支援事業の一環として運営する“里親サロン”の活動から見えてきた現状と課題を報告。遺児・孤児の受け入れ家庭のピアサポートづくりの場としてのサロン。「里親さんたちは、相談できる人や場所が非常に限られています」「子育て経験も無いのに突然“里親”になってしまった方々もいるのです」「超高齢者の里親たちは、自分たちが居なくなった後のことを心配しています」と、あまり支援対象として注目されない“里親子”たちへの支援の必要性を強調。「昨年からDVや虐待の通告が増加している。予防的支援として“社会的養護”は非常に重要です」「同じひとり親家庭でも、父子家庭と母子家庭に支援の差が出てしまっている。支援の偏りをなくしていき、地域での見守り体制をつくっていく必要があります」と卜藏氏は訴えました。
福島県から参加した、日本ユニセフ協会が震災発生直後からサポートを続けている『親子ふれあい遊び』を運営する福島県臨床心理士会の成井香苗氏は、「震災発生時に新生児だった現3歳児と、当時3歳だった現小学校1年生の間に、発達障害などの可能性を指摘されているケースが多くなっている」と報告。「親との愛着が一番必要な時期に、親自身が安定していなかったこと、また子どもを外に出せないことで、子どもたちが運動不足やストレスを抱え、落ち着きがない、衝動的・乱暴な行為など、ADHDを疑うような行動が増えるのではないか」と分析します。こうした状況の改善と予防のために、親子の愛着形成や、お母さん同士の交流を促すため続けられている『親子ふれあい遊び』。時に“心のケア”と一言で説明されがちな活動ですが、子どもたちの発達に必要な複合的な支援を提供するために、地域の保健士や保育士、臨床心理士、栄養士、助産士など、多職種の協働で成り立っていることの重要性を強調されました。
里親子支援
14日の特別シンポジウムでも指摘された“親族里親”への支援の必要性は、翌15日の『被災地の親族里親支援から見えるもの〜日本における親族里親支援の現状と課題〜』と題する分科会でも報告されました。
日本ユニセフ協会が全国児童家庭支援センター協議会と連携して実施している「里親子支援プロジェクト」では、岩手県里親会の里親サロンに連携して里親子レスパイト交流キャンプ事業をサポート。分科会では、これらの活動内容やそこから見えてきた課題が報告。また、議論は、被災地から日本国内の親族里親全般の現状に関わる問題に及びました。
現在国内では、県が“社会的養護”を、市町村が“子育て支援”をそれぞれ管轄しています。里親子の支援に重要な役割を果たすふたつの施策。分科会では、県と市町村の連携の重要性が指摘されました。また、諸外国と比較して限定的な「親族里親」の定義が、日本における親族里親の課題や親族里親への支援の必要性を希薄化させているのではという指摘もあがりました。また、里親にとっては休息であり子どもたちにとっては「複数の養育者たちとの出会いの場」となる「レスパイトキャンプ」の継続性も含め、被災地にとどまらず日本全体の親族里親支援にも関わる課題が提示されました。
 緊急・復興支援活動 2年レポートはこちらから[7.2MB] »
緊急・復興支援活動 2年レポートはこちらから[7.2MB] »
 寄付方法のご案内
寄付方法のご案内
 ご寄付による支援例・成果
ご寄付による支援例・成果
 領収書
領収書
 その他のご協力方法
その他のご協力方法
 個人のみなさま
個人のみなさま
 学校・園のみなさま
学校・園のみなさま
 大学生ボランティア
大学生ボランティア











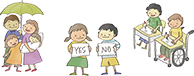
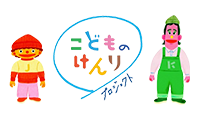







 緊急・復興支援活動 2年レポートはこちらから[7.2MB] »
緊急・復興支援活動 2年レポートはこちらから[7.2MB] »